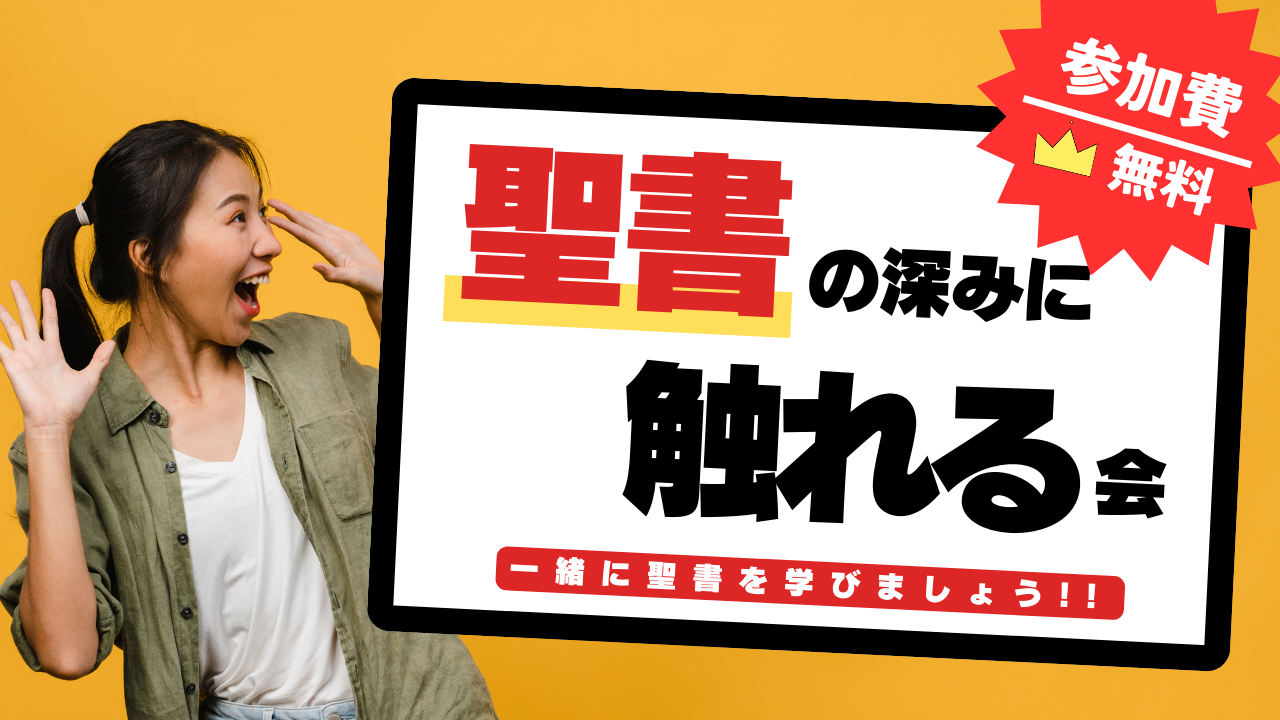(この記事は5,924文字で、12分で読み終えることができます。)
現代の多くのクリスチャンは、日曜日が「安息日」であると考えています。しかし、それは誤った聖書解釈です。この誤解は、聖書に啓示されている真理を曇らせてしまいます。この記事では、まず聖書の啓示に基づき、安息日についての考えを深めましょう。そして、「安息日」と「主日」との違いを明らかにし、私たちがどのような立場で歩むべきかを見ていきます。もし、あなたがまだ日曜日は「安息日」であると考え、それを守っているなら、あなたは恵みの下にではなく律法の下に歩んでいるかもしれません。聖書の中で神が私たちに与えられた真の安息とは何か、主日とは何かを、一緒に見ていきましょう
神は六日かかって天地万物を造り終え、第七日にはすべてのわざをやめて安息されました。その約2,500年の後、神は十戒を与えられました(出エジ20:1-17)。その中の第四の戒めは、人に安息日を記念させるものであり、神のみわざを記念させるものです。この安息日の記念は、神が世界を回復した時、六日間で回復を終え、第七日に安息されたことを、人に振り返って見させるものです。ですから、第七日はもともと神が安息された日です。ここから約2,500年余り経ってから、神はこの第七日の安息日を人に与えて、人もまた安息するようにさせたのです。
旧約の事柄は、すべてきたるべき素晴らしい事柄の影にすぎません(ヘブル10:1)。神が人に安息日を与えられたことも、旧約のその他の多くの予表と同様に、霊的な意義があります。神は第六日に人を造り、第七日に安息されたのですから、人は造られるとすぐに働いたのではなく、まず神の安息の中へと入り込みました。人はまず安息し、その後はじめて働いたのです。これが福音の原則です。ですから、安息日は福音の予表です。安息が働きの前にあること、これが福音です。
安息日の意義は、人が働かずにただ神の安息に入り込むことです。人が神の安息に入り込むとは、人が自らの働きをやめ、神のみわざを受け入れることです。人が安息日を犯すことは、大きな事柄ではないかのように見えますが、神の真理から言えば、それは実に大きな事柄です。人はまず福音を受け入れるべきであり、そうしてこそ行うことができます。人が安息日を犯すとは、自分自身で働くことができ、自分自身で行うことができるということであり、つまり、神のみわざを必要としないことの表示です。安息日を守ることは、何もしないということではなく、人が神の安息の中で安息し、神のみわざを受け入れることです。これが旧約においての安息日がわたしたちに見せていることです。
Ⅰ. 主日は安息日ではない
新約に入ると状況は変わりました。主イエスは安息日に会堂に入られ、聖書を読まれました(ルカ4:16)。彼は会堂に入って、人に教えられました(マルコ1:21)。使徒たちもまた安息日に会堂に入って、聖書について説きました(使徒17:1-3)。このことから、安息日には消極的な休みがあるだけでなく、積極的な働きがあることを見ることができます。もともとそれは体を休める日でしたが、新約になるとそれは霊的な事柄を追求する日と変わりました。これは一つの前進です。
もしわたしたちがよくよく聖書を読むなら、聖書における神の啓示は進歩していることを見いだすことができます。以前の聖書を読むための四つの基本原則と実践的ガイド – 聖書の読み方 – 初信者シリーズ 7 の記事で、聖書を読む時には「事実を探し出す必要がある」ことを語りました。それは、事実の中に光があるからです。事実に変更があったのですから、新しい光があるのです。安息日についてもそうです。
聖書は創世記において「神はその第七日目を祝福し」(創世記2:3)と言っています。しかし、主イエスが復活された時、聖書は「週の初めの日」(マタイ28:1)と言っています。聖書は主イエスの復活の日を「第七日目」とは言わずに「週の初めの日」と言っています。これは神が「週の初めの日」を「安息日」に代えられたと言っているのではありません。しかし、神がわたしたちの注意を転じて、「週の初めの日」に心を向けるようにと願っていることを聖書ははっきりと見せています。
安息日は福音の予表です。福音の実際であるキリストが来たので、その予表は過ぎ去りました。安息日の原則は福音です。それはささげ物の原則が十字架であるのと同様です。旧約でささげ物に用いられた牛や羊は、みな神の小羊である主イエスを予表しています。主イエスが来られたので、牛や羊は用いられなくなりました。もし今日も牛や羊を引いてきてささげ物にするなら、それは十字架を認識していないということです。同様に、福音はすでに来たのですから、人は福音によって神の御前で安息することができるのです。神は、ご自身の御子の十字架上での贖いを通して、わたしたちのためにすべてのみわざを成し遂げてくださったのですから、神はわたしたちという人が先に何かをするように命令されるのではなく、まず安息するようにと命じられたのです。今日、牛や羊のささげ物がないように、安息日もありません。安息日は旧約における予表です。新約では、この予表はすでに成就したのです。
Ⅱ. 主日の根拠
旧約では、神は七日間の一日、すなわち第七日を選び、それを聖なる安息日と定められました。新約になると、旧約の第七日はすでに過ぎ去りましたが、七日間の中から一日を選ぶ原則はやはり継続しています。しかしながら、新約には別の日があります。安息日が主日になったのではありません。旧約の時、神は一週の中から第七日を選ばれました。新約では、神は一週の中から第一日を選ばれたのです。神は第七日を第一日と呼んだのではなく、別の日を第一日とされました。
詩篇第118篇22節から24節はとても重要です。「家を建てる者たちの捨てた石、それが隅のかしら石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。これは、主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼう」(原文)。ここに「家を建てる者たちの捨てた石」という言葉を見ます。石が役に立つかどうかは、家を建てる者たちの決めることです。家を建てる者たちがこの石は使えないと言えば、それは使えないのです。しかし、不思議なことがあります。神は彼を、すなわち「家を建てる者たちの捨てた石」を、「隅のかしら石」とし、土台とされました。神は最も重要な責任を彼の上に置かれたのです。24節はさらに不思議な言葉です。「これは、主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼう」。これは家を建てる者たちの捨てた石が隅のかしら石となった日こそ、主が設けられた日であると言っています。
それでは、どの日が主の設けられた日なのでしょうか?使徒行伝第4章10節から11節は言います、「あなたがた一同も、イスラエルのすべての民も知っていただきたい。あなたがたが十字架につけ、神が死人の中から復活させたナザレ人イエス・キリストの御名の中で、この名の中で、この人が、あなたがたの前に健やかになって立っているのです。この方は、あなたがた、家を建てる者たちに捨てられ、隅のかしらになった石です」。10節は、「あなたがたが十字架につけ、神が死人の中から復活させた」と言い、11節は、「あなたがた、家を建てる者たちに捨てられ、隅のかしらになった石です」と言います。家を建てる者たちが捨てた時とは、主イエスが十字架につけられた時です。神が彼を隅のかしら石とされた時とは、神が彼を死人から復活させた時です。言い換えれば、この石は、主イエスの復活の時に、隅のかしら石となったのです。ですから、「主の設けられた日」とは、主イエスの復活の日です。
ここでわたしたちが見るのは、わたしたちの主日は、旧約の律法の下にある安息日とは全く異なっています。旧約の安息日は、これをしてはならない、あれはすべきではないと、みな消極的です。しかし、神は新約時代に設けられた主イエスの復活の日は、楽しみ喜ぶようにと言っておられます。ですから、主日の特徴は、積極的な命令があるだけであって、消極的な命令はないのです。
七日間の中から神は特に一日を選び出し、この日を特別な名前で呼んでいます。啓示録第1章11節はそれを「主日」と呼んでいます。「主日」は聖書で述べられている「主の日」であるという人がいますが、それは間違っています。原文では「主日」と「主の日」とは全く異なります。「主日」は週の第一日であり、「主の日」は主の再来の日です(第一テサロニケ5:2、第二テサロニケ2:2、第二ペテロ3:10)。もう一面において、古代の教父たちの著作から、「主日」が週の第一日を指し、教会の集会の日とされていることを証明する多くの材料を見つけることができます。古代教父たちの著作の中の多くの資料が、初代教会の時代から第四世紀までずっと週の第一日に集会していたことを証明しています。古代の教会の主日に関する資料
Ⅲ. 主日は何をすべきか
主が設けられた日である主イエスの復活の日、すなわち、週の第一日(主日)にわたしたちは何をすべきなのでしょうか?主日に何をすべきかについて聖書は、三つのことを重要視しています。第一は、喜び楽しむこと。第二は、主を記念すること。第三は、主にささげものをすることです。一つ一つを詳しく見ていきましょう。
1. 楽しみ喜ぶ
詩篇118篇24節は言います、「これは、エホバが設けられた日である。わたしたちは喜び躍り、それを喜び楽しもう」。ここに啓示されているように、すべての神の子たちが週の第一日に取るべき態度は、喜び楽しむことです。わたしたちの主は死から復活されました。これは主が設けられた日(主日)であり、わたしたちはこの日が来るたびに喜び楽しむという態度を持ち続ける必要があります。この日はわたしたちの主の復活の日であり、このような日は他にありません。ですから、主日に喜び楽しむことは自然な反応であるべきです。
2. 主を記念する
第二に、使徒行伝第20章7節は言います、「そして週の初めの日、わたしたちがパンをさくために集まった時・・・」。原文の文法によれば、ここの「週の初めの日」は、ある週の初めの日を限定して指しているのではなく、彼らが毎週の初めの日にパンをさくために集まったことを意味します。当時すべての教会は、週の初めの日になると自然にパンをさくために集まって、主を記念していました。週の初めの日は、わたしたちが主にまみえる日です。週の初めの日に必ずしなければならないことは主を記念することです。わたしたちが週の初めの日にまず主の御前に行くのです。主日は週の第一日です。月曜日は実は週の第二日です。
パンさきには、聖書では二つの意義があります。一つは主を記念することであり、もう一つはわたしたちと神のすべての子供たちとの間に交わりがあることを表明することです。パンさきについてはさらに詳しく書いた記事があるので、こちらをご覧ください。
3. 主にささげものをする
コリント人への第一の手紙第16章1節と2節は言います、「聖徒たちへの贈り物を集めることについては、わたしがガラテヤの諸召会に指示しておいたように、あなたがたも行いなさい。週の初めの日に、各自は得た繁栄に応じて手元に蓄えておき、わたしが行った時に集めることのないようにしなさい」。ここで、週の初めの日になすべき第三の事をみます。パウロはここでガラテヤに在る各教会に指示しておいたように、コリントに在る教会にも指示しています。これは使徒たちの時代には、週の初めの日が特別な日であったことを明らかに示しています。週の初めの日にはパンをさいて主を記念することがあり、また聖徒たちのために献金することがあります。週の初めの日ごとに、各自はその経済的に恵まれたところに応じて主にささげるべきです。一方でパンさきがあり、一方で献金があります。一方でわたしたちは主がどのようにご自身をわたしたちに与えてくださったかを記念し、もう一方でわたしたちもまた、この日に主にささげるのです。
わたしたちは、何も考えないで少しのお金を取り出して献金箱に投げ入れるべきではありません。真心をもって家でよく計算し、家で準備し、あるいは家で包んで、敬虔な方法で献金箱に入れるべきです。パウロはここで、献金は計画的になすもの、定期的になすものであることを見せています。週の初めの日ごとに、自分の経済的に恵まれたところに応じて取り出し、主に言う必要があります、「主よ、あなたはこんなにも豊かに与えてくださいました。主よ、わたしは得たものからあなたにささげます」。恵みが多ければ多く献金し、少なければ少なく献金します。パンさきは厳粛な事であり、献金もまた厳粛な事であることを、知らなければなりません。
まとめ
主は特別に一週の中から一日を取り出して、それを主日と呼んでいます。それは週の初めの第一日です。ですから、わたしたちの日曜日に位置する日は主日です。わたしたちの主日と安息日は異なります。安息日はしてはいけない事に重きがあります。しかし、わたしたちの主日は、体の安息のためではなく、働きのためでもありません。他の日にやってよい事は、主日にも行うことができます。他の日にやってはいけない事は、主日にもやってはいけません。
聖書は、主日に喜び楽しむようにと、もっぱら主の御前に来て恵みを受け、主を記念し、主に仕え、ささげるようにと告げています。わたしたちは一生の間、この主日を取り出して特別な日としなければなりません。少なくとも週の初めの日はすべて取り出して、主のためとしなければなりません。この日はわたしたちの日ではありません。この日は「主日」です。この時間は、わたしたちの時間ではありません。この時間は、主の時間です。この日は主にささげた日であり、それを主日と呼ぶのです。
ヨハネは啓示録でこのように言いました。
わたしは主日に霊の中にいた。
啓示録 1章10節
どうか多くの人が、「わたしは主日に霊の中にいた」と言う事ができますように。
参考資料
ウォッチマン・ニー全集 第三期 第四十八巻 初信者を成就するメッセージ(一)第十四編
出版元:日本福音書房
※ 本記事で引用している聖句に関して、明記していなければすべて回復訳2015からの引用です。
「オンライン聖書 回復訳」