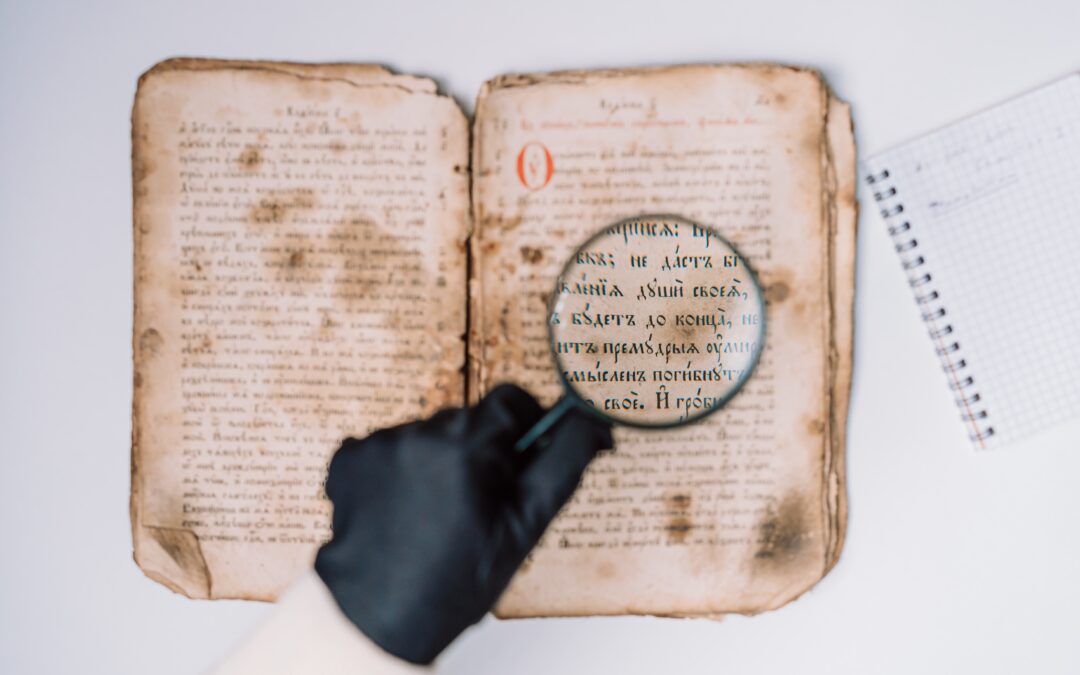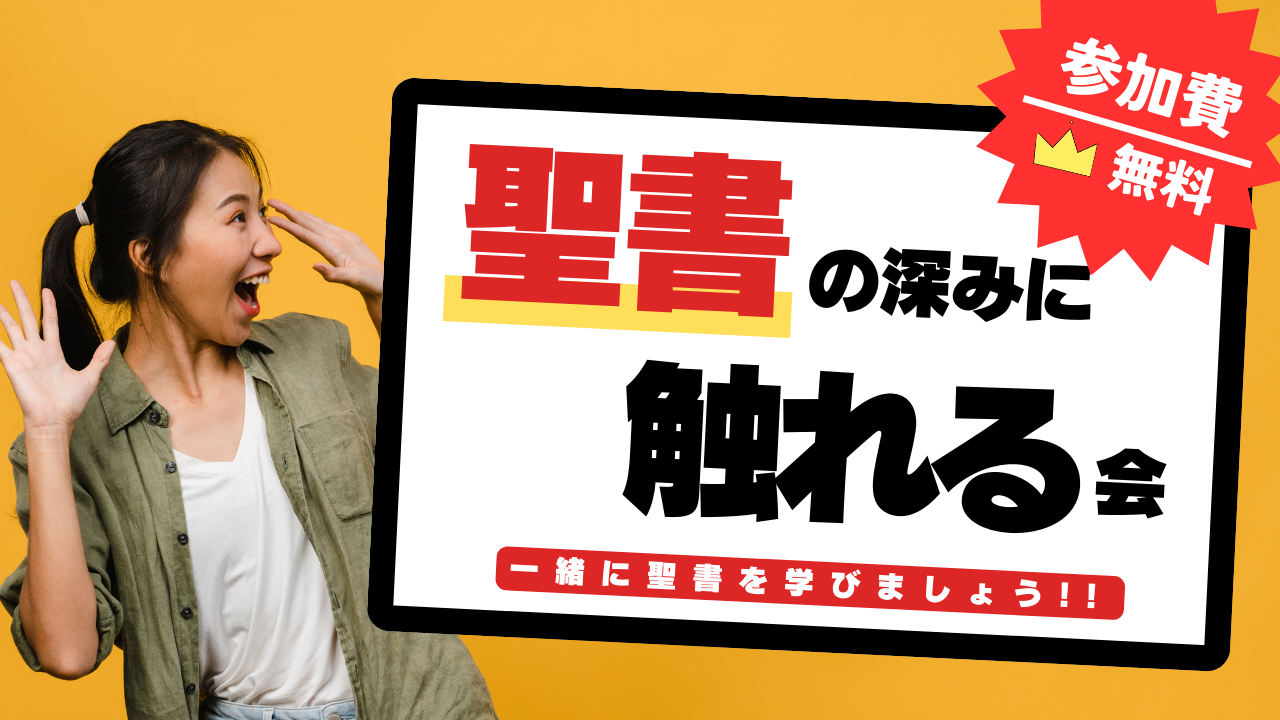十二使徒の教え(紀元75-90年)
主日に関しては、「十二使徒の教え」(聖書以外の最初の教会の書物であり、およそ紀元七十五年から九十年の間に書かれたものであり、少なくとも啓示録と同時代のものである)という書物の中に、以下のような言葉があります、「主日ごとに、あなたがたは共に集まって、自分の罪を告白した後、パンをさき、感謝をささげなければなりません。そうすれば、あなたがたがささげるささげ物は清められます」。これは、信者が主日の集会において、第一世紀の終わりごろにこのようにしていたことをはっきりと見せています。
イグナチウス(紀元100年)
使徒ヨハネに一人の弟子がおり、その名をイグナチウスと言い、彼は紀元三十年に生まれ、紀元百七年に殉教しました。彼は紀元百年の時、一通の手紙をマイニシア地方の者に書き送りました。この一通の手紙の第九章の中で、彼ははっきりと言っています、「あなたがたは昔の教える人(ユダヤ教の人たちを指す)にしたがって、第七日の安息日を守ることは、もはや今日すべきではありません。主日を守るべきです。なぜなら、その日にわたしたちの命は彼と共に発芽したからです」。これもまたはっきりと、初期の教会が安息日を守っていたのではなく、主日を守っていたことを見せています。
バルナバ(紀元120年)
およそ紀元百二十年にバルナバ(聖書に出てくるバルナバではない)が書いた一通の手紙の第十五章に次の一句があります、「わたしたちは喜んで第八日、つまり主イエスが死から復活された日を守ります」。
エスティノス(紀元138年)
さらにもう一人の教父がおり、人は彼のことを殉教者エスティノスと呼び、教父たちの中ではかなり有名な人です。彼は紀元百年に生まれ、紀元百六十五年に殉教しました。紀元百三十八年の時、彼は「弁証論」という書物を書きました。その書物の中で彼は言っています「日曜日つまり週の初めの日に、すべて町に住んでいる者とその町以外に住んでいる者は共に集まり、みなで使徒の伝記と預言者の著作を読みます。時間が許す限り、読めるだけ読みます。読み終わったら、数句の教える言葉があれば、導く兄弟が、それらの良い事に習うようにとみなに勧めをします。後ほどわたしたち全体は立ち上がって祈り、祈り終わったらパンとぶどう酒を持ってきて、導く人が祈りと感謝をささげ、全員が心を一つにして「アーメン」と言います。富んでいる人も、心から喜んでささげる人も、各自はその感謝にふさわしい額をささげます。それを集めて処理する人に託し、その人が孤児や寡婦、病人、必要のある人、捕らわれている人、わたしたちの間で集会している人を顧みます。言い換えれば、必要のあるすべての人を顧みるのです。日曜日はわたしたちの普通の集会の日です。なぜなら、イエス・キリスト、わたしたちの救い主がこの日に死から復活されたからです。主は土曜日の前日に釘づけられ、土曜日の翌日、つまり日曜日に彼の使徒や弟子たちに現れ、彼らにこの事を教えられました。今日この事をあなたがたに書き送るので、それを考慮するようにしてください」。さらにもう一箇所で彼は言っています、「わたしたちは罪と過ちの中から、わたしたちの主イエス・キリストを通して割礼を受けました。彼は週の初めの日に、死から復活されました。ですから、この日はすべての日の中で主要な日、第一日となったのです」。
メリト(紀元170年)
紀元百七十年、サルデスに在る教会に、メリトと呼ばれた教父がいました。彼の書いた本の中に光のような一句があります、「わたしたちは今日、主の復活の日を過ごしています。この時わたしたちは多くの手紙を読みます」。
クレメンス(紀元194年)
紀元百九十四年、アレクサンドリア市にクレメンスという有名な教父がいました。彼は炎のように言いました、「第七日は今日、働きの日となっています。それはまた普通の働きの日でもあります」。続けて彼はまた言っています、「わたしたちは主日を守るべきです」。
テルトゥリアヌス(紀元200年)
紀元二百年、教父テルトゥリアヌスは言いました、「主日に、わたしたちは特に喜びに満たされます。わたしたちはこの日を、すなわち主の復活の日を守ります。妨げもなく、心配事もありません」。そのころすでに、主日を守ることは太陽を礼拝することであると批判する人がいたので、テルトゥリアヌスは彼らに答えて言いました、「わたしたちは主日に喜びます。わたしたちは太陽を礼拝しているのではありません。わたしたちは、怠けて土曜日に宴会しているような人たちとは異なります」。
オリゲネス
オリゲネスは、教父たちの中でも有名な一人ですが、彼はアレクサンドリアの有名な神学者です。彼は、「主日を守ることは完全なクリスチャンであることのしるしです」と言っています。
週の初めの日は安息日ではない
ある人は、古代の信者たちは安息日を守っていたのであり、第四世紀にコンスタンティヌスが週の初めの日を守るように改めさせたのである、と言います。これは事実に合いません。コンスタンティヌスは、この日を改めたのではなく、この事実を認めたのにすぎません。というのは、教会はすでに長い間、主日を守ってきていたからです。紀元三百十三年の前までは、クリスチャンは迫害を受けました。紀元三百十三年の後、コンスタンティヌスはローマを支配し、ミラノ地方で一つの詔書を発布し、クリスチャンを迫害することを禁じました。紀元三百二十一年、コンスタンティヌスは第二の詔書を発布し、言いました、「主日には、役人も一般民衆も、町に住む者はみな休むべきであり、すべての仕事は停止すべきである」。
この詔書の中でコンスタンティヌスは、初めから終わりまで安息日には全く触れておらず、ただ週の初めの日が教会の日であることを認めただけでした。
以上の資料の中から、主日を守ることは、使徒と教会の教父たちの時から始まり、これが各時代の実行であったことを知ることができます。
参考資料
ウォッチマン・ニー全集 第三期 第四十八巻 初信者を成就するメッセージ(一)第十四編
出版元:日本福音書房