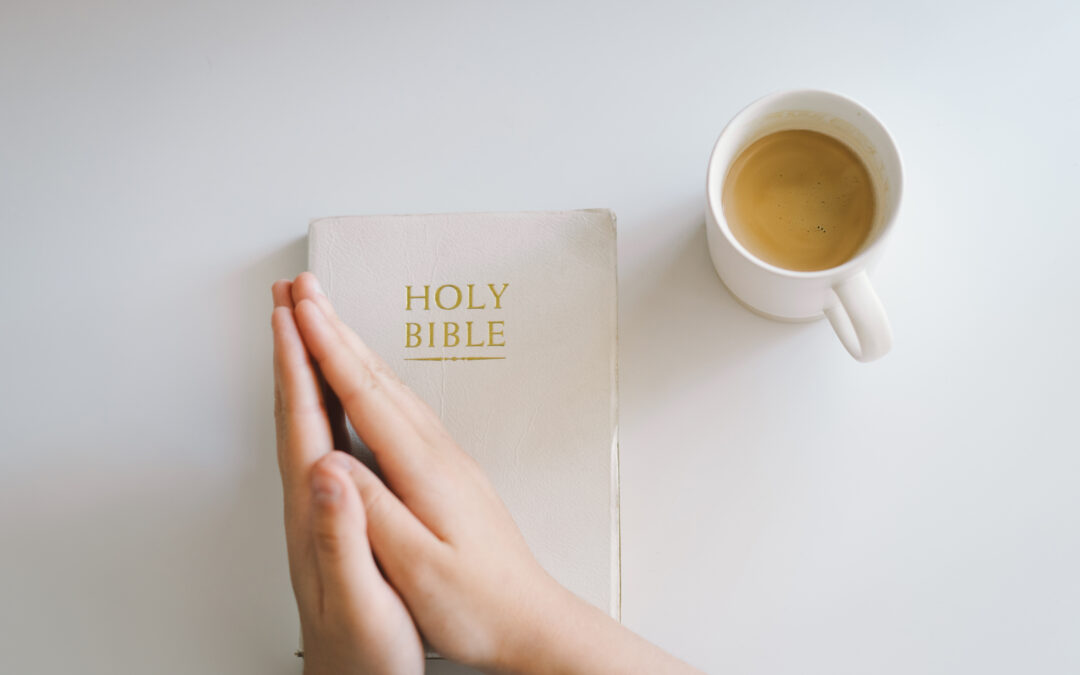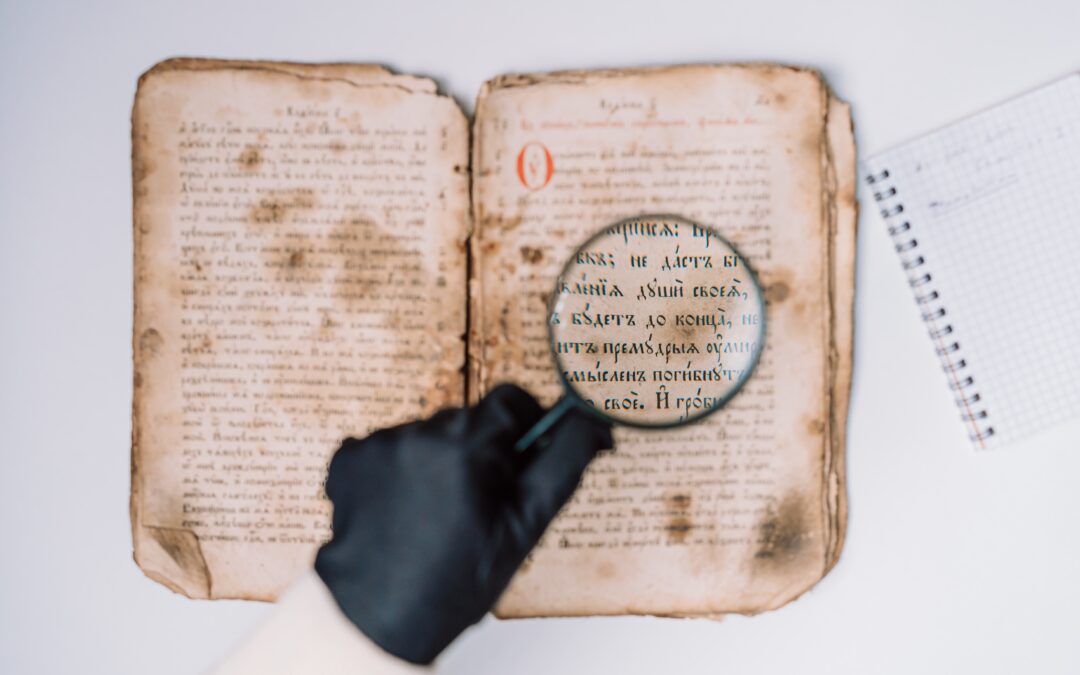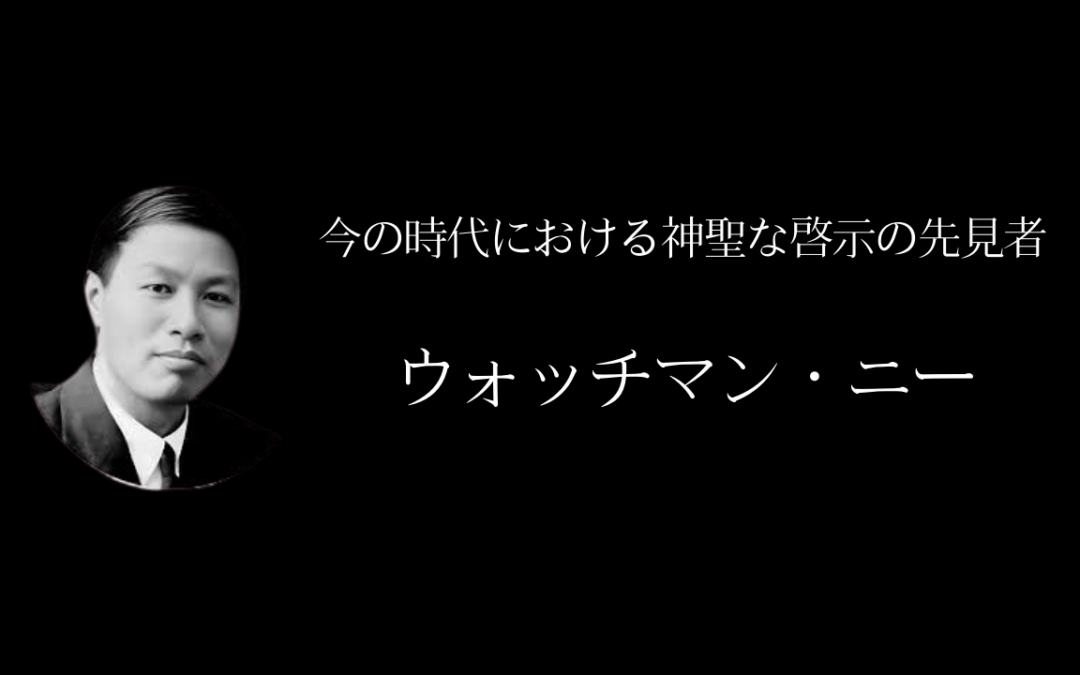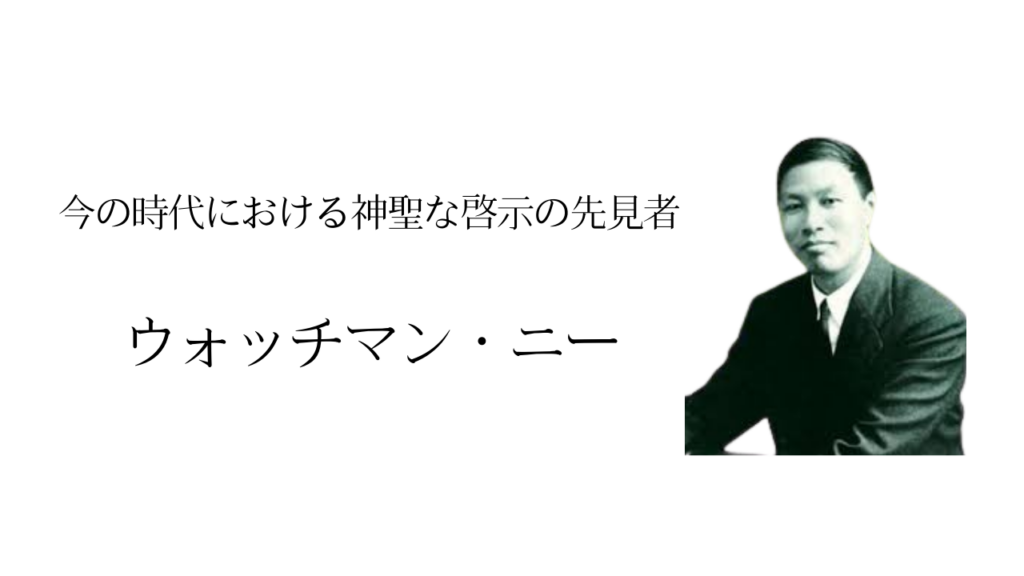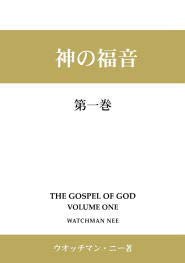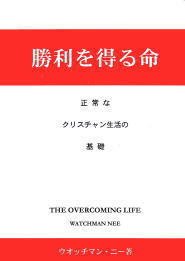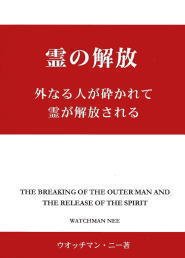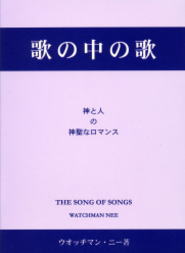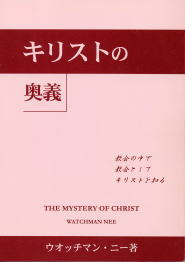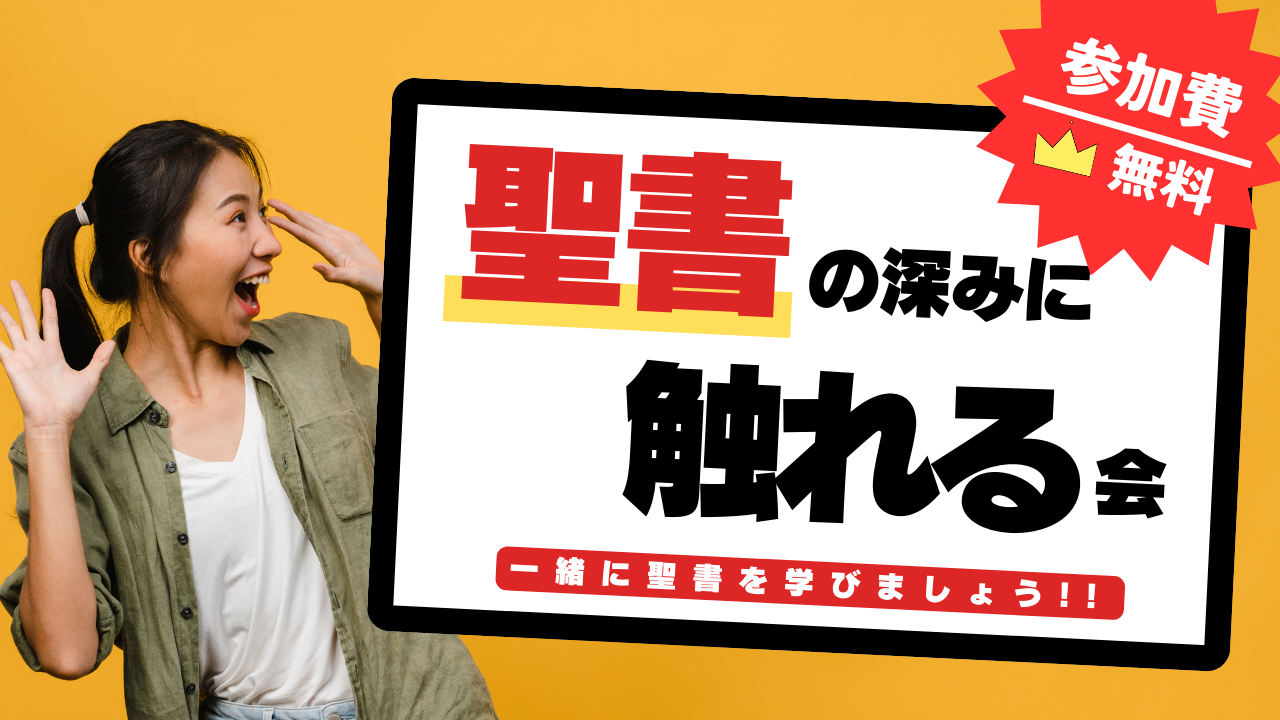2025-05-04 | 初信者成就シリーズ
(この記事は9,981文字で、20分で読み終えることができます。)
「祈っているのに答えがない…」。もしあなたがこのように悩んでいるなら、それは賛美をする時です。賛美は、神の子たちの最高の働きです。あるいは霊的命の最高の表示が神を賛美することであると言ってもよいでしょう。神の御座は宇宙の中で最も高い所にあり、神は「イスラエルの賛美の上に座しておられる」(詩篇22:3 原文)のです。神の御名、神ご自身は、賛美によって高く挙げられるのです。
ダビデは詩篇の中で、一日に三度神に祈ると言いました(詩篇55:17)。また、一日に七度、神を賛美するという詩も書きました(詩篇119:164)。ダビデは聖霊に感動されて、賛美がいかに重要なことであるかを告白したのです。祈りは一日に三度ですが、賛美は七度です。こればかりでなく、彼はまたあるレビ人たちを任命して、神の契約の箱の前で、シンバルを鳴らさせ、琴を弾かせ、神をあがめ、感謝し、ほめたたえました(歴代上16:4-6)。ソロモンがエホバの宮のすべての工事を終えた時、祭司たちは契約の箱をかついで至聖所に入りました。祭司たちが聖所から出てきた時、歌を歌うレビ人たちがいて、祭壇のそばに立ち、ラッパを吹き、歌を歌い、さまざまな楽器をもって、声を張り上げ、神を賛美しました。その時、エホバの栄光が神の宮を満たしました(歴代下5:12-14)。ダビデとソロモンは神のみこころに触れて、神に喜ばれる賛美をささげたのです。エホバはイスラエルの賛美の上に座しておられるのですから、わたしたちは生涯、神を賛美し、わたしたちの神をほめたたえるべきです。
Ⅰ. 賛美のいけにえ
聖書は賛美に多くの注意を払っており、またとても多く出てきます。その中でも、詩篇は多くの賛美の言葉で満ちています。詩篇は旧約の賛美の書です。多くの人の賛美は、この詩篇から採られたものです。しかし、詩篇は単に賛美の書であるだけでなく、苦難の書でもあることに注意してください。神が特にわたしたちに見せたいのは、賛美する人とは、神によって苦難な状況を通らせられ、傷ついたと感じている人たちであることです。多くの聖徒たちが神によって暗やみへと導かれ、人に捨てられ、悪く言われ、迫害されました。「あなたの波とあなたの大波はみな、わたしの上を超えて行きます」(詩篇42:7)が、それによってこの人たちの上で神は賛美を得られたのです。賛美の言葉は順調な人の口から出てくるのではなく、訓練を受け、試みを受けた人の口から出てくるのです。詩篇では、最も傷つけられた感覚に触れることができ、またそれゆえに詩篇では、賛美の声は最も大きく、また最も高いのです。神の民が多くの患難、多くの苦しみ、多くの非難を通る時に、神は彼らの上で賛美を造り出し、彼らにそのような環境において神の御前で神を賛美する人となることを学ばせるのです。
ですから、一番喜んでいる人の賛美の声が一番高いのではなく、常に神の御前で困難を通っている人たちの賛美が最高なのです。そしてこのような賛美が、最も神に喜ばれ、最も神の祝福を受けるのです。神が人を高い山に立たせて、顔をカナンに向かわせ、約束の地を見せる時、そこに賛美の声があるだけでなく、人が「死の陰の谷を歩む」(詩篇23:4)時にも、詩を書くことができ、賛美することができることを願っておられます。これが神の賛美です。
このことは、神の御前での賛美の性質はどのようなものであるかを見せています。賛美の性質は一つのいけにえ、一つの犠牲です。言い換えるなら、賛美とは、患難や苦難の中から出てくるものです。ヘブル人への手紙第13章15節ではこのように言っています、「ですから、彼を通して、絶えず賛美のいけにえ、すなわち、御名を言い表す唇の実を、神にささげようではありませんか」。いけにえとは何でしょうか?いけにえとは犠牲であり、死と損失があるのです。いけにえをささげる人は、損失があってはじめてささげることができます。元々ここの一頭の牛や羊はあなたのものでしたが、今日それをささげてしまえば、この一頭の牛あるいは羊をあなたは犠牲にしたことになります。ささげることは、得ることではなく、失うことです。
聖徒たちが賛美をささげる時には、失ったものを一つのいけにえとして神にささげるのです。言い換えれば、神があなたを傷つけ、あなたを砕き、あなたを深く切り裂く時、あなたに神の御前に来て賛美して欲しいのです。このように自分が傷つけられて神に賛美を得させる行為、これがいけにえです。神は、このようにしてご自身を賛美する人を喜ばれるのです。神はこのような賛美を御座とすることを喜ばれます。神はどのような賛美を得たいのでしょうか?神は、神の子たちが自分の損失したものをもって神を賛美することを願われます。何かを得た時に賛美するのではありません。もちろん、これは賛美ですがいけにえではありません。いけにえの原則は、損失に根拠があり、いけにえには損失という性質がなければなりません。神は、わたしたちが損失を受けてもなお賛美できることを願われます。
わたしたちは神の御前で祈るだけでなく、神の御前で賛美する人となることを学ぶべきです。あなたはどこにいても絶えず神を賛美すべきです。ダビデは神の恵みにより、一日に七度神を賛美しました。わたしたちが毎日賛美できるとしたら、これはとてもよい学びであり、とてもよい学課であり、とてもよい霊的訓練です。朝早く起きた時に神を賛美し、何か事に出くわした時に神を賛美し、集会の時に神を賛美し、一人でいる時に神を賛美することを、わたしたちは学ぶべきです。一日に少なくても七回神を賛美すべきです。
あなたが主の御前で賛美することを学んでいる時、ある日、賛美が出てこなくなるでしょう。今日は七度神を賛美することはでき、昨日も七度神を賛美することができたでしょう。その前の一週間は神を賛美することができましたし、その前の一ヶ月間も、神を賛美できたでしょう。しかし、ある日賛美することがなくなるのです。なぜなら、その日は苦しい日であり、一筋の光もなかった日であり、とても良くないことがあった日であり、多くの無実の罪を着せられ、多く非難された日なので、涙を流しても足りないのに、神を賛美することなどできるはずがないと思っているのです。その日になると、あなたは自分の受けた傷、苦痛、苦難のゆえに、賛美することができないでしょう。それどころか、賛美よりもつぶやきたいと自然に感じ、神の御前で感謝ではなく不平を言うことでしょう。賛美したいなどとは思わず、賛美する心さえないでしょう。そのような環境の中で、そのような心境で賛美することはふさわしくないと感じるでしょう。そのような時、あなたは思い出す必要があります。エホバの御座は変わらないし、主の御名も変わらないし、主の栄光も変わらないのです。あなたは彼を賛美すべきです。なぜなら、彼は当然賛美を受けるべき方であるからです。あなたは彼をほめたたえるべきです。なぜなら、彼はほめたたえられるべき方であるからです。あなたは苦難に遭っているでしょうが、彼はやはり賛美を受けるべき方です。あなたは困窮しているかもしれませんが、神を賛美しなければなりません。そのような時にこそ、あなたの賛美は賛美のいけにえとなるのです。あなたの賛美は最も肥えた子牛を引いてきてほふるかのようであり、またあなたの愛するイサクを縛って祭壇の上にささげるかのようです。あなたは涙を流してそこで賛美します。これが賛美のいけにえです。いけにえとは、傷つけられること、死、損失、犠牲です。あなたが神の御前で傷を受け、死に、損失を被り、犠牲がある時、あなたが神の御座は天に堅く定まっており、永遠に揺り動くことがないことを見るなら、神を賛美せざるを得ないでしょう。これが賛美のいけにえです。神はご自分の子たちがどのような事においても、どのような状況の中でも、よくよく神を賛美するのを喜ばれます。
Ⅱ. 賛美と勝利
これまで賛美が一つのいけにえであることを見てきました。それだけでなく、賛美がわたしたちの霊的戦いに勝利を得る方法であることを見る必要があります。しばしばある人は、サタンの最も恐れるのは神の子たちの祈りであり、いつであれ神の子たちがひざまずいて祈る時にサタンは逃げ去るのであって、だからサタンはいつも神の子たちを攻撃して祈れないようにすると言います。これは通常の攻撃にすぎません。わたしたちが知る必要があることは、サタンが最も攻撃するものは祈りではなく賛美であるということです。サタンは色々と悩まし、祈りはそんなに簡単ではないと感じさせます。これは確かに事実です。しかし、サタンは祈りを攻撃するだけでなく、神の子たちの賛美をさらに攻撃します。祈りは多くのとき戦いですが、賛美は勝利なのです。祈りは霊的戦いですが、賛美は霊的勝利です。いつであれ賛美する時、サタンは必ず逃げ去ります。ですから、サタンは賛美を最も憎み、できることなら全勢力を費やしてでもわたしたちが賛美できないようにしようとしているのです。神の子たちが愚かであれば、自分の環境を見、自分の感覚を見て、賛美をやめてしまいます。神の子たちが神を認識すればするほど、ピリピの獄中でさえ歌うことのできる場所であることを見るでしょう(使徒16:25)。パウロとシラスはそこで神を賛美していた結果、獄の扉がみな開いてしまったのです。
使徒行伝には、獄の門が開いた例が二つあります。一度はペテロの上で、もう一度はパウロの上でです。ペテロの時には、教会が彼のために熱心に祈った結果、御使いが門を開き、ペテロを連れ出しました(使徒12:3-12)。パウロとシラスの場合、彼らは神を賛美していたところ、獄の扉が全部開き、鎖がすべて解けてしまいました。その日、全家族が救われて喜びました(使徒16:19-34)。そこには、獄の中で賛美のいけにえをささげている人たちがいました。体の傷はまだ良くなっていませんし、その痛みも止まっていません。しかも両足にはかせがはめてあり、ローマの獄の中に閉じ込められていたのです。どうして喜ぶことができるでしょうか?どうして歌うことなどできるでしょうか?しかし、そこにいた二人の霊はとても高く引き上げられ、すべてを超越していました。彼らは、神が天に座しておられ、変わることがないことを見ていました。自分たちは変わるし、その環境も変わるし、その感覚も変わります。しかし、神はやはり御座に座しておられ、ほめたたえられるにふさわしい方です。そこで、兄弟パウロとシラスは祈り、歌い、神を賛美しました。このような賛美は、彼らの苦痛から出てきたものであり、このような賛美がいけにえなのです。このような賛美がまた勝利でもあるのです。
あなたは祈る時、その境遇の中にいますが、賛美する時はその境遇の上に立ってしまっているのです。わたしたちがそこで祈り、切に求めている時は、まだその事の中におり、出てきていません。あなたが神の御前で切に求めれば求めるほど、その事に縛られてしまい、その事があなたの上にのしかかってくるのがわかるのでしょう。しかし、もし神によって引き上げられて、獄を超越し、鎖を超越し、体の傷の痛みを超越し、その苦痛と恥辱を超越するなら、その時に声を上げて神の御名を歌いほめたたえることでしょう。パウロとシラスが歌ったことは、神の御前で賛美の言葉を歌っていたことです。彼らは、獄など問題にせず、恥辱も苦痛も問題にならないところまで神によって導かれたので、神の御前で賛美することができたのです。彼らがそのように賛美した時、獄の扉はすべて開き、鎖は落ち、獄吏も救われたのです。
多くの時、祈ることはできないのですが、賛美はできます。これは基本的原則です。もし祈ることができないなら、なぜ賛美しないのですか?主はもう一つのものをわたしたちの手の中に置いて、勝利を得させ、勝ちどきを上げさせてくださるのです。祈る力がなく、霊がとても圧迫され、完全に傷つき、息ができないほどあえぐ時、神を賛美してみてください。祈る事ができれば祈り、祈れなければ賛美してください。わたしたちは、荷が重い時に祈り、荷が取り去られる時には賛美すると思いがちです。しかし、多くの時、荷が重くて祈ることができない時こそ、賛美すべきなのです。荷がなくなってから賛美するのではなく、荷が最も重い時に賛美するのです。もし大変な事に遭い、問題が多すぎて、全身が麻痺してしまったようになり、どうしていいかわからないような時、「なぜ賛美しないのですか?」という言葉を思い出してください。それはとても良い機会なのです。すなわち、そのような時に賛美するなら、神の霊が働いてあなたを導き、すべての門を開き、鎖を全部取り去ってくださいます。
わたしたちは、この高く超越した霊、攻撃を超越した霊を維持することを学ばなければなりません。祈りではいつでも御座に触れることができるとは限りませんが、賛美ではどんな時であっても必ず御座に触れることができます。祈りでは毎回勝利することができるわけではありませんが、賛美は初めから終わりまで一度も失敗はありません。神の子たちは、物事がなく、感覚がなく、傷がなく、問題がない時に口を開いて賛美するだけでなく、特に問題のある時や、傷つけられた時こにこそ、もっと賛美すべき時なのです。そのような時、あなたは頭を上げて、「主よ!あなたを賛美します!」と言ってください。目から涙が流れるでしょうが、口は賛美することができます。心は傷ついていても、霊は賛美することができます。最も愚かな人は、つぶやく人です。つぶやけばつぶやくほどその中に埋もれ、不平を言えば言うほどその中に落ち込み、困難に圧迫されればされるほど息もつけなくなるでしょう。少し進んだ人たちは、問題に遭う時に祈るでしょう。彼らはそこで奮闘努力し、そこから抜け出そうとします。環境は彼らを埋めてしまおうとし、感覚も彼らを埋めてしまおうとします。彼らは埋められたくないので、祈りによって脱出しようとします。しかし、多くの時、祈りも脱出させることができません。彼らが賛美する時にやっと脱出するのです。あなたが自分自身を勝利の地位に置けば、すぐにすべてのものを超越し、どんな問題もあなたを埋めてしまうことはできないでしょう。
歴代志下第20章20節から22節を見ましょう、「彼らは朝早く起きて、テコアの荒野に出て行った。その出て行くとき、ヨシャパテは立ち上がって言った、『ユダと、エルサレムの住民よ、わたしに聞きなさい。エホバ・あなたがたの神を信じなさい.そうすれば堅くされる.彼の預言者を信じなさい.そうすれば成功する』。彼は民と相談して、エホバに歌い、聖なる飾り物を着けて感謝をささげる者たちを立てた.彼らは軍勢の前に出て行って、こう言った、『エホバに感謝をささげよ、彼の慈愛は永遠に続く』。彼らが歌って叫び、賛美し始めたとき、エホバは伏兵を設けて、ユダに攻めて来たアンモン、モアブ、セイル山の子たちを襲わせたので、彼らは討たれた」。ここには戦いがあります。ヨシャパテがユダの王となった時、ユダ王国はすでに傾きかけていて、とても弱く、すべては惨めな状態にありました。モアブ人、アンモン人、セイル山の人々がユダの人々を攻めに来た時、ユダの人々は全く希望を失い、打ち破られて滅亡してしまうに違いないと思いました。ヨシャパテは復興された王であり、神を畏れる人でした。もちろん最後の時期のユダの王ですから、それほど完全ではなかったとしても、彼はやはり神を求めた人でした。彼はユダの人々に、神を信じるべきであると言いました。そして、歌を歌う人を任命して、主を賛美させたのです。この歌を歌い、主を賛美する人たちに、聖なる飾り物を着けさせ、前に進ませ、主を賛美させて、「エホバに感謝をささげよ、彼の慈愛は永遠に続く」と言わせました。
次の節の中の「賛美し始めたとき」という言葉に注意してください。これはとても尊い言葉です。「彼らが歌って叫び、賛美し始めたとき、エホバは伏兵を設けて、ユダに攻めて来たアンモン、モアブ、セイル山の子たちを襲わせたので、彼らは討たれた」。「賛美し始めたとき」とは、彼らが歌を歌い、主を賛美しているちょうどその時に、主が立ち上がってアンモン人、モアブ人、セイル山の人々を殺されたということです。わたしたちは、賛美ほど主の御手を動かすものはないと言わなければなりません。主の御手を動かす最も早い方法は祈ることではなく、賛美することです。これは祈りが不必要であると言っているのではありません。やはり祈る必要があります。しかし、多くのことで賛美して勝利する必要があるのです。
わたしたちがここで見るのは、霊的勝利は戦いによるのではなく、賛美によるということです。わたしたちは賛美によってサタンに勝利することを学ばなければなりません。ここでの特別な原則は、霊的勝利は戦いによるのではなく、賛美によるということです。
神の子たちの多くはとても厳しい試練を常に受けています。試練が厳しく、戦いが激しい時は、ヨシャパテのように道がないかのようです。自分を見、環境を見れば、最大の試練です。しかし、神を認識している人は、試練を受ければ受けるほど主を仰ぎ、また賛美することを学びます。そうすれば、頭を上げて主に言うでしょう、「主よ!あなたはすべてを超越しておられる方です。あなたを賛美します!」このような賛美のいけにえは神の御前で効力のあるものです。賛美する時、あなたは勝利の道がどんなに大きいかを見るでしょう!
わたしたちは賛美の学課を学ぶ必要があります。困難に遭う時は、神があなたの手段を禁じ、あなたの計略を差し止めてくださり、賛美の学課を学べるようにあわれみを求めましょう。戦いがどれほどあっても、すべて賛美によって勝利することができます。勝利できないのは、賛美に欠けているからです。もし困難の中にあっても神を信じるなら、このように言ってください、「あなたの御名を賛美します。あなたはすべてにまさって高く、すべてにまさって強く、あなたの慈しみはとこしえに絶えることがありません!」。神を賛美する人はみな、すべてを超越していますから、賛美によってずっと勝利し続けることができるのです。これが原則であり、事実です。
Ⅲ. 信仰が賛美を生む
詩篇106篇12節の言葉はとても尊いです、「そこで、彼らはみことばを信じ、主への賛美を歌った」。これはイスラエル人が荒野にいた時の情景です。彼は信じたので、歌いました。彼らは信じたので、賛美しました。賛美には信じるという基本的な内容があります。困難がある時にあなたは祈り、また悩みがある時に祈るでしょう。祈りが一定の時に達すると、信じることができるようになり、そうすれば口を開いて賛美するでしょう。あなたは立って、困難に対してもサタンに対しても、口を開いて「主よ!あなたを賛美します!」と言うなら、感覚がなかったのにあるようになり、ほんのわずかの信仰も満ち溢れるようになります。わたしたちは何かが終わってから、達成されてから賛美するのではなく、信じた時に賛美するのです。敵が逃げ去って歌うのではなく、歌うことで敵を追い払うのです。信じてはじめて賛美できます。それから勝利が来るのです。
Ⅳ. 服従が賛美を生む
わたしたちの問題はたいてい二種類あります。一つは、環境や出来事の中の問題であり、ヨシャパテのような問題です。これには、神を賛美することによって打ち勝ちます。もう一つは、わたしたちの内側の問題であり、ある人の言葉によって傷つけられるとか、ある人がわたしたちにすまないことをしたとか、欺いたとか、理不尽に扱ったり、逆らったり、理由なく恨んだり、根拠なく非難したりして我慢できないとか、赦せないようなことです。これは個人が勝利する問題です。
ある兄弟があなたに言うべきでないことを言ったとします。それは辛いことです。全身がもがき、全身が不平を言い、全身がつぶやいているかのようです。あなたは赦すことは何と難しいことであり、寛容であることは何と難しいことであり、打ち勝つことは何と難しいことであるかと感じます。罪を着せられ、非難され、迫害されて内側ですっきりしない時には、祈りはあまり効果がありません。その気持ちは防ぎ止めようと思っても止まらず、もがいてももがき切れないのです。この圧迫を拒絶しようとすればするほど、駄目になります。
覚えておいてください。このような個人的な問題にぶつかり、ひどく罪を着せられる時は、祈る時ではなく、賛美する時です。こうべを垂れて主に、「主よ、感謝します。あなたのなさることに間違いはありません。わたしはあなたの御手からこれを受け取ります。感謝します。あなたの御手からいただいたこのことのゆえに、賛美します」と言うべきです。もしこのようにするなら、すべてが過ぎ去ってしまうでしょう。勝利は、自分が肉と争って人を赦そうとして、そのために力を尽くすことによるのではなく、こうべを垂れて、主を賛美して、「主よ、あなたの道を賛美します。あなたがわたしのために備えられたものに間違いはありません。あなたがなさることはすべてすばらしいのです」と言うことによります。傷つけられたと思っている人は賛美の少ない人です。これこそ服従から生まれる賛美のいけにえです。
Ⅴ. はっきりと理解する前に賛美する
詩篇50篇23節は言います、「だれでも感謝の犠牲をささげる者は、わたしに栄光を帰する」。ここの「感謝」は「賛美」とも訳せます。主はわたしたちの賛美を待っておられます。賛美ほど神に栄光を帰するものはありません。ある日、すべての祈りは過ぎ去り、すべての働きも過ぎ去り、すべての預言者の言葉も過ぎ去り、すべての労苦も過ぎ去るでしょう。しかしその日、賛美は今より増すでしょう。賛美は永遠に続き、永遠にやむことはないでしょう。ですから、最も良い学課は、今日の時に神を賛美することを学ぶことです。
今日わたしたちは鏡に映すように見ており、おぼろげであまりはっきりしてはいません(Iコリ13:12)。多くのことで少しは見ることはできても、その中の意味は何であるかをはっきりと知り尽くすことはできません。わたしたちの遭遇すること、経過すること、内側で受けた傷であろうと、外側の状況の困難であろうと、わたしたちは苦しさを感じるだけで、その意味がはっきりとわからないので、賛美できないのです。天上で多くの賛美があるのは、天上には完全な認識があるからだと信じます。認識が完全であればあるほど、賛美も完全になります。
わたしたちが主の御前に行く日には、すべてのことがはっきりするでしょう。その日には、どの聖霊の管理もすばらしい意図があったことを見るでしょう。わたしたちはこれらを見る時、こうべを垂れて、賛美し、「主よ、あなたには間違いがありません」と言うでしょう。あの時、病気になっていなかったら、わたしはどうなっていたことだろう。あの時、失敗していなかったら、わたしはどうなっていたことだろう。その日になれば、なぜ主がこのような目に遭わせたのかがわかるでしょう。その日になれば、頭を下げて言うことでしょう、「主よ、わたしは愚か者です。あの日には賛美しませんでした。わたしはあの日、あなたの前で感謝しなかった愚か者です」。その日になってはっきりわかってから、どんなにつぶやいたかを思って、どれほど悔やむことでしょう。ですから今日、「主よ、あなたのなさることは、わたしにはよくわかりません。しかし、わたしはあなたのなさることに間違いはあり得ないことを知っています」と言うことを学びましょう。
エホバは彼のすべての道において義であり、彼のすべての行ないにおいて慈しみがあります。 詩篇145篇17節
わたしたちの賛美は彼の栄光です。賛美することは、神に栄光を帰することです。神は栄光を受けるべき方です。どうか神がご自身の子たちから多くの賛美をお受けになりますように。
参考資料
ウォッチマン・ニー全集 第三期 第四十九巻 初信者を成就するメッセージ(一)第十六編
出版元:日本福音書房
※ 本記事で引用している聖句に関して、明記していなければすべて回復訳2015からの引用です。
「オンライン聖書 回復訳」

2025-04-27 | 初信者成就シリーズ
(この記事は6,555文字で、13分で読み終えることができます。)
わたしたちは主を信じた後、必ず罪を告白する習慣、負債を償う習慣を持つべきです。もしだれかに対して罪を犯すなら、あるいはだれかに損害を与えるなら、罪を告白する、あるいはそれを償うことを学ぶべきです。一方で、わたしたちは神の御前で罪を告白しなければなりません。そして他方では、人に対しても罪を告白したり、償ったりしなければなりません。もしこの両方を行わないなら、この人の良心は容易に神の御前でかたくなになってしまいます。良心がかたくなになってしまうと、神の光がその人を照らすのが難しくなってしまいます。
主の働きをしていたある兄弟は、いつも次のように人に聞いていたものです、「あなたが最後に人に対して罪の告白をしたのはいつですか?」。もしその人が最後に罪の告白をしてから長い時間が経っており、それが数年になるとしたら、その人の良心はきっと問題があることでしょう。なぜなら、わたしたちはしばしば人に対して罪を犯してしまうものですが、もし罪を犯しても何の感覚もないとすれば、これはその人の良心が病気であり、正常でない証拠です。わたしたちが神の光の中で生きようとする時、感覚のある良心が必要となります。なぜなら、良心の感覚があれば、神の御前で継続して罪を罪とすることができるからです。
もしその罪がただ神に対するもので、人とは関係がないなら、人に対して罪を償う必要はありません。わたしたちは度を越してまでするべきではありません。どのような兄弟姉妹であれ、その犯した罪がただ神に対するものであって、人とは関係がない場合は、神に罪を告白すればよいのであって、人に罪を告白する必要は決してありません。
それでは、どのような罪が人に対する罪なのでしょうか?また人に対して罪を犯し、損害を与えた時は、どのようにして罪を告白し、負債を償えばよいのでしょうか?これらを詳しく見ていきましょう。
Ⅰ. レビ記第六章にある違反のためのささげ物
違犯のためのささげ物には二つの面があります。レビ記第5章で記されているものと、第6章で記されているものです。第5章では、こまごまとした罪に関して、神の御前で罪を告白し、ささげ物をささげて、赦しを請うべきことを言っています。第6章では、もし何か物質的に人に対して罪を犯すなら、神の御前にささげ物をするだけでは不十分で、その罪を犯した相手に対して弁償すべきであることを言っています。レビ記6章の違犯のためのささげ物の記述から見ることができますが、もしわたしたちが物質的に人に対して罪を犯したなら、その人のところに行って、その罪を取り扱うべきです。もちろん神の御前に行って罪を告白し、赦しを請うべきですが、ただ神の御前で取り扱うだけで、人の前に行って対処しないなら、対処したことになりません。神に対して、その相手に代わって自分の犯した罪を赦してくださるように求めるわけにはいかないのです。
A. 人に対する違犯である罪
レビ記第6章2節から7節は言います、「人が主に対して罪を犯し、不実なことを行うなら」(すべての罪は、究極的にはエホバに対する違犯です)、「すなわち預かり物や担保の物、あるいはかすめた物について、隣人を欺いたり、隣人をゆすったり、あるいは落とし物を見つけても、欺いて偽りの誓いをするなど、人が行うどれかについて罪を犯すなら、この人が罪を犯して罪に定められたときは、そのかすめた品や、強迫してゆすりとった物、自分に託された預かり物、見つけた落とし物、あるいは、それについて偽って誓った物全部を返さなければならない。元の物を償い、またこれに五分の一を加えなければならない。彼は罪過のためのいけにえの日に、その元の所有者に、これを返さなければならない。この人は主への罪過のためのいけにえを、その評価により、羊の群れから傷のない雄羊一頭を罪過のためのいけにえとして祭司のところに連れて来なければならない。祭司は、主の前で彼のために贖いをする。彼が行なって罪過ある者とされたことのどれについても赦される」。ここから、人が物質的な事柄において誰かに対して罪を犯したり、違犯を犯すなら、それを人の前で解決しなければなりません。
次の六つの節は、人に対する六種類の違犯を述べています。第一に、隣人から預かった物について欺く場合です。わたしたちは人から預かった物について欺くべきではないばかりか、むしろ誠意をもって保管すべきです。第二は、担保の品について欺くことです。これは物の売り買いについて欺くとも言えます。これは正当でない手段を使って自分の利益を図り、本来自分のものとはならないはずのものを自分のものにしてしまうことです。第三は、人の財産を奪うことです。他の人の物を自分の物とすることは罪です。第四は、隣人をしいたげることです。人が地位や権力を用いて他の人を圧迫し、自分に都合よくしてしまうことは罪です。第五は、落とし物を拾い、それについて欺くことです。クリスチャンは人のものを拾うべきではありません。もし拾うなら、本人に代わって保管し、何とかしてそれを本人に返す手立てを見つけなければなりません。第六に、偽って誓うことです。明らかに知っているのに知らないと言い、明らかに見ているのに見ていないと言い、明らかに有るのに無いということなどは偽りの誓いをすることです。
ここでの罪はすべて、物について人に借りを作ることを指して言っています。神の子たちとして学ぶべき基本的なことは、他の人のものを自分のものにしてはならないということです。これらの罪はよくよく対処しなければなりません。
B. どのようにして返済するか
わたしたちは神の御前で正しい行いと、咎めのない良心を保持することを学ばなければなりません。ここで神の言葉は、「この人が罪を犯して罪に定められたときは、そのかすめた品・・・を返さなければならない」と言っています。神の御前で「なだめられた」から十分であると思ってはなりません。人に対して「返す」ことがなければ、十分ではありません。返してはじめて十分なのです。
それでは、どのようにして返したらよいのでしょうか?5節は言います、「元の物を償い、またこれに五分の一を加えなければならない。彼は罪過のためのいけにえの日に、その元の所有者に、これを返さなければならない。」ここには注意すべき点が三つあります。
第一は、残りなく償うことです。これは必ずすべてを返済しなければならないということです。第二は、残りなく返済することに五分の一を加えるということです。原則は、余るほど十分に返済しなければならないということです。神はご自分の子たちがただ最低限度をするだけでは満足されません。負債を償う時は、けちけちするのではなく、余裕をもって十分にすべきです。五分の一を加えることは、人に罪を犯すことは損失を被ることであることを思い知らせます。このことを見るなら二度と同じことをしないでしょう。
第三は、このように罪を告白することや返済することは、早ければ早いほどよいのです。ここでは、「彼は罪過のためのいけにえの日に、その元の所有者に、これを返さなければならない」と言っています。あなたは過失が明らかになったその日に罪を告白し、返済すべきです。遅らせてはいけません。
このように返済してもまだ十分ではありません。6節は言います、「この人は主への罪過のためのいけにえを、その評価により、羊の群れから傷のない雄羊一頭を罪過のためのいけにえとして祭司のところに連れて来なければならない」。ですから、その人に罪を告白し、償いをした後、やはり神の御前に行って赦しを求めなければなりません。レビ記第5章の違犯のためのささげ物は、物質的には人に負債を負っていないので、ただ神の御前に出てそれを対処すれば十分でした。しかしレビ記第6章は人に対して負債のある場合ですから、人の前ではっきりと対処してはじめて、神の御前に出て赦しを求めることができます。まだはっきりと対処していないのに、神の御前に出て赦しを求めることはできません。
これは浅薄なことであると思ってはいけません。わたしたちの天然の性質は極みまで堕落しています。もし少しでも不注意であるなら、容易に罪を犯してしまうでしょう。ですから、これは一生の間ずっと注意していなければならないことです。
Ⅱ. マタイによる福音書第五章の教え
次に、マタイによる福音書第5章を見ましょう。マタイによる福音書第5章とレビ記第6章で述べられていることは、異なっています。レビ記第6章で述べられているのは、完全に物質的な負債についてであり、マタイによる福音書で述べられているのは、単なる物質的な負債以上のことです。
マタイによる福音書第5章23節から26節は言います、「だから、あなたが自分の供え物を祭壇にささげようとし、あなたの兄弟が自分に対して何か恨みを持っていることを、そこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に残しておき、まず行って、兄弟と和解しなさい。それから戻ってきて、あなたの供え物をささげなさい。あなたを訴える者と共に道を行く間に、彼と早く仲直りしなさい。そうでないと、その訴える者はあなたを裁判官に引き渡し、そして裁判官は役人に引き渡して、あなたは獄に投げ込まれる。まことに、わたしはあなたに言う。あなたが最後の一コドラントを払ってしまうまでは、決してそこから出てくることはできない」。ここで言っている一コドラントとは、単に物質的なものを指すのではなく、その負い目について語っているのです。
主は言われます、「だから、あなたが自分の供え物を祭壇にささげようとし、あなたの兄弟が自分に対して何か恨みを持っていることを、そこで思い出したなら、・・・」。これは特に神の子たちの間でのこと、兄弟と兄弟との間のことについて述べています。あなたが神に対してささげものをしようとする時、突然、兄弟が自分に対して何か恨みを抱いているのを思い出します。この「思い出す」とは、神があなたに与えた導きです。多くの時、この種のことについて、聖霊は必要な思いをあなたの内に置きます。これを単なる思い込みだと思ってはなりません。そのことを思い出したなら、直ちにしっかりと対処しなければなりません。
もし兄弟が自分に対して何か恨みを抱いていることを思い出したなら、それはあなたに何か負い目があるからに違いありません。兄弟に対する負い目とは、物質上でないことかもしれません。もしかすると、気がつかないうちに彼に罪を犯したのかもしれません。ここでのポイントは、他の人に恨みを抱かれているということです。
これをよくよく理解していただきたいのですが、もしだれかに罪を犯したのに、過ちを認めず、赦しを求めなければ、その相手の人が神の御前であなたの名前を挙げてため息をつくだけで、もうあなたは終わりです。なぜなら、あなたが神にささげたものはすべて受け入れられませんし、あなたがささげる祈りもすべて聞かれないからです。もしあなたが一つのことを行い、それが誤りであり、不義であって、他の人に罪を犯し、他の人を傷つけてしまうなら、その人は神の御前に行ってあなたを訴えることをしなくても、神の御前に行って一言、「ああ、あの人は」と言うだけで、あなたのささげものはすべて受け入れられないものとなってしまいます。
もし、あなたがこのことを思い出したなら、「まず行って、兄弟と和解しなさい。それから戻ってきて、あなたの供え物をささげなさい。」です。これは兄弟と和解しなければ、あなたの神へのささげものは永遠に受け入れらないことになるということです。
ですから、軽々しく人に罪を犯してはなりません。特に、兄弟姉妹に対しては軽々しく罪を犯してはなりません。主のここでの一句は非常に重要です、「あなたを訴える者と共に道を行く間に、彼と早く仲直りしなさい」。わたしたちは、神の裁きの御座へと向かっています。今日わたしたちはみなこの道の途中にいます。彼はまだ世を去っていませんし、あなたも世を去っていません。ですから、早く彼と和解しなければなりません。ある日、あなたがここにおらず、この道からいなくなり、あるいは彼がここにおらず、この道からいなくなるその日が容易に訪れるからです。救いの門は永久に開いているのではありませんし、兄弟たちが互いに罪を告白しあう門も永久に開いているのではありません。
それに引き続いて、主は人の言葉を用いて語っておられます、そうでないと、その訴える者はあなたを裁判官に引き渡し、そして裁判官は役人に引き渡して、あなたは獄に投げ込まれる。まことに、わたしはあなたに言う。あなたが最後の一コドラントを払ってしまうまでは、決してそこから出てくることはできない」。「裁判官に引き渡し」とは、キリストが再来される時、彼の裁きの座の前で起こります(Ⅱコリント5:10)。裁判官は主であり、役人は御使いであり、獄は懲らしめの場所です。ローマの一コドラントは、一アサリオンの四分の一に当たる小さな銅の貨幣であって、日本円で一円に等しいです。ここの意味は、最も小さいことについても、わたしたちは徹底的に清算する必要があるということです。ですから、もしわたしたちが救われた後に、罪を犯し、それを悔い改めず、和解もしないなら、キリストの再来の時に裁かれ、獄の中で懲らしめを受けるということです。すべての聖徒がこのことをはっきりと見ますように。
Ⅲ. 実行の時に注意すべき幾つかの点
人に対する罪を償おうとする時、注意すべき点が幾つかあります。第一に、罪を犯した範囲にしたがって罪を告白するということです。神の言葉にしたがって行う時に、極端な道を走ってはなりません。度を越すと、今度はサタンの攻撃を受けてしまいます。第二に、罪を告白するときは徹底的にすべきです。しかし、ある時には相手からの益となるように、別の人の益となるために、どのように罪を告白すれば最も良いかをよくよく尋ね求めるべきです。かなり複雑な状況では、経験のある兄弟姉妹と交わることが良いでしょう。
第三に償いにおいて、時としてそれらすべてを償う力がないかもしれません。しかし、償う力がないことと、心から償おうとすることは別のことです。誠意を持って、相手の人に理由を説明し、どのようにすべきかを問うべきです。第四に、もしも償いを受け取るべき人がすでに世を去っていて、その償いを受け取る親族もいないときは、その償うものを、エホバに仕える祭司に帰さなければなりません(民数記5:8)。もしあなたの償いを受け取る本人がいないときは、その償いは彼の親族に帰します。もし親族が一人もいない場合は、教会に渡してもよいでしょう。
第五に、罪を告白し償った後は、良心の訴えを受けないように特に気を付ける必要があります。ある人は、償いのためにずっと訴え続けれられることがよくあります。ですから、主の血が良心を洗い清めたこと、主の死があなたに神の御前で汚れのない良心を持たせたことをひたすら見続けなければなりません。あなたが徹底的に罪を対処したなら、サタンに過度な訴えをさせてはいけません。
第六に罪の告白といやされることは関係があります。ヤコブの手紙第5章16節は言います、「ですから、互いにあなたがたの罪を告白し合い、互いに祈り合いなさい。それは、あなたがたがいやされるためです」。罪を告白した結果は、神が病気をいやしてくださることです。
もし罪を犯した部分があれば、一面、神の御前で罪を告白し、もう一面、人の前で真剣に対処しなければなりません。そうすれば良心は強くなるでしょう。良心が強くなってこそ、霊的な道の上で前進ができるのです。
参考資料
ウォッチマン・ニー全集 第三期 第四十九巻 初信者を成就するメッセージ(二)第二十二編
出版元:日本福音書房
※ 本記事で引用している聖句に関して、明記していなければすべて回復訳2015からの引用です。
「オンライン聖書 回復訳」
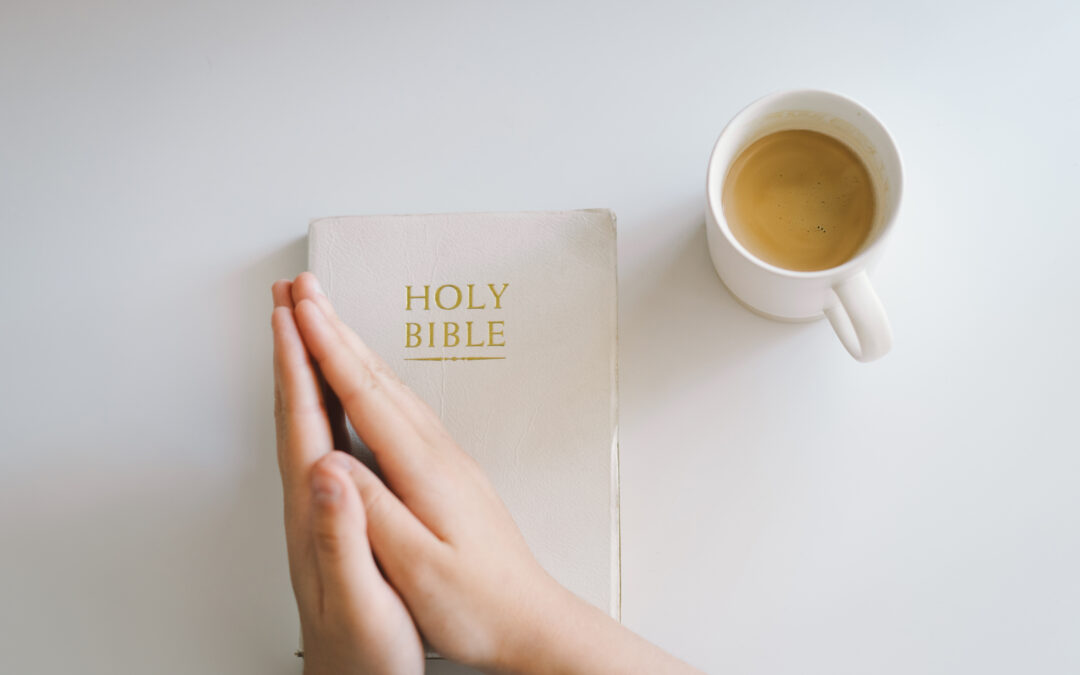
2025-04-20 | 初信者成就シリーズ
(この記事は7,327文字で、15分で読み終えることができます。)
わたしたちは救われた後、再び罪を犯すべきではありません。ヨハネによる福音書第5章で主イエスは、ベテスダの池で38年間病んでいた人をいやされ、その後、主は彼を宮の中で見つけられ、彼に言われました、「見よ、あなたは良くなった。もう罪を犯してはいけない。もっと悪いことがあなたに起こらないためである」(ヨハネ5:14)。ヨハネによる福音書第8章では、主イエスは一人の淫婦を赦され、その場で彼女に言われました、「今後はもう罪を犯してはいけない」(ヨハネ8:11)。ですから、わたしたちが救われると、主はわたしたちに、もう罪を犯してはいけないと一つの命令をされます。すでに救われたわたしたちは、断じて罪の中に生きてはいけません。
Ⅰ. 救われた後に罪を犯す問題
クリスチャンであるなら、罪を犯してはいけませんし、断じて罪の中に生きてはいけません。しかし、クリスチャンは罪を犯さないことができるのでしょうか?できます!!!あなたに言いますが、クリスチャンは罪を犯さないことができるのです。なぜなら、わたしたちの中には神の命があるからです。この命は罪を犯さず、この命は少しも罪に譲歩することがありません。神が聖であられるように、この命も聖です。もしわたしたちがこの命の感覚にしたがって生きるなら、もしこの命の中で生きるなら、わたしたちは罪を犯すことがありません(Ⅰヨハネ3:9)。
しかし、クリスチャンにも罪を犯す可能性があります。なぜなら、わたしたちはまだ肉体の中にいるからです。もし聖霊にしたがって行動しないなら、もし命の中で生きないなら、いつでもどこででも罪を犯す可能性があります。ガラテヤ人への手紙題6章1節は言います、「兄弟たちよ、たとえだれかが、何かの違犯に陥ったとしても・・・」。ヨハネの第一の手紙第2章1節は言います、「わたしの小さい子供たちよ、・・・もし誰かが罪を犯すなら・・・」。このことから、クリスチャンは依然として、違犯に陥ることがあり得ること、罪を犯すことがあり得ること、を見ることができます。
それでは、人が救われた後に、もし不幸にも罪を犯してしまったなら滅びてしまうのでしょうか?滅びることはありません!なぜなら、主は言われたからです、「わたしは彼らに永遠の命を与える。彼らは決して永遠に滅びることはない。まただれもわたしの手から、彼らを奪い去りはしない」(ヨハネ10:28)。言い換えると、人は主イエスを信じ、救われたなら永遠に救われるということです。またコリント人への第一の手紙第5章は、一人の兄弟が淫行の罪を犯したことに言及しており、パウロは次のように言っています、「そのような者を、彼の肉を破壊させるためにサタンに渡したのです。それは、彼の霊が主の日に救われるためです」(Ⅰコリント5:5)。これもまた、人が救われた後に罪を犯してしまうなら、彼の肉は滅ぼされるとしても、彼の霊はやはり救われるということを言っています。
このようであるなら、救われた後に罪を犯すということは別に構わないことなのでしょうか?そうではありません!!!救われた後に罪を犯すなら、三つの恐るべき結果があるのです。第一は、この世において苦痛を受けることです。救われた後に罪を犯すなら、必ず罪を犯した結果が生じます。ちょうどコリント人への第一の手紙第5章が言っているように、このような者をその肉が破壊されるためにサタンに引き渡すのです。これは一つのとても大きな苦痛です。ある罪を犯した後に、もしあなたが罪を悔い改め、罪を告白するなら、神はあなたを赦し、血はあなたを清めるでしょうが、罪の結果を免れる方法はありません。ダビデがウリヤの妻をめとったということについて、エホバは彼の罪を除かれましたが、剣はいつまでも彼の家を離れなかったのです(サムエル下12:9-13)。罪は楽しいおもちゃではなく、あなたが罪を犯すなら必ず苦痛を受けます。
第二は、来るべき世において刑罰を受けることです。もしクリスチャンが罪を犯し、この時代においてそれを正しく対処しなければ、来るべき時代になった時にそれを対処しなければなりません。主が再来される時、「それぞれに、行いにしたがって報いられるからである」(マタイ16:27)とあります。またパウロは言います、「なぜなら、わたしたちはみな、キリストの裁きの座の前に現れなければならないからであり、それは善であれ悪であれ、めいめいが実際に行った事にしたがって、体を通してなされた事柄に対して、報いを受けるためです」(Ⅱコリント5:10)。
第三は神との交わりが断たれるということです。クリスチャンが神と交わることができるということは、最も栄光な権利であり、また最大の祝福でもあります。しかし、クリスチャンが罪を犯すなら、すぐに神との交わりを失ってしまいます。彼の喜びは失われ、神との交わりも失われてしまいます。以前は、祈ることや聖書を読むことにとても味わいがありましたが、今は味わいがなく、神に触れられません。それは神の臨在を失うことです。
ですから、救われた後に罪を犯すことは、とても重大なことです!わたしたちは、わたしたちの行いを絶対にいい加減にすることのないようにしなければなりません。しかし、「もしだれかが罪を犯すなら」、どうすればよいのでしょうか?もしあなたが不幸にも罪を犯してしまったなら、どうすればよいのでしょうか?どのようにすれば神との交わりが回復されるのでしょうか?これはとても重要な問題です。わたしたちはよくよくこの問題を見る必要があります。
Ⅱ. 主はわたしたちのすべての罪を担われた
この問題を解決するのに、第一に見なければならないことは、主イエスが十字架上に釘づけられた時、彼はわたしたちのすべての罪を担われたということです。主イエスが十字架上でわたしたちに代わって担われたものは、すべての罪を含んでいるのです。わたしたちが一生において犯す罪、過去のものだけでなく、現在のものも、将来のものも、主は十字架上で完全にわたしたちに代わって担われたのです。
あなたが24歳で救われたとしても、あなたが救われる前の多くの罪を主はすべて赦してくださったと、あなたは確かに感じるでしょう。しかし、あなたがそこで赦された時、あなたが赦されたと感じる罪は、実際に主によって担われた罪ほど多くありません。わたしたちは、わたしたちが感じていない罪も、主イエスの贖いの中に含まれていることを、知る必要があります。言い換えれば、主は十字架の上でわたしたちの全生涯の罪を担われたということです。
Ⅲ. 赤い雌牛の灰の予表
わたしたちは、主イエスが十字架上でわたしたちの全生涯の罪を担われたということをどのようにして知ることができるのでしょうか?それは旧約の民数記第19章の赤い雌牛の灰の予表によって見ることができます。民数記第19章は、旧約の中で特別な章です。
2節で神はモーセとアロンに言われました、「イスラエルの子たちに告げて、欠陥がなく、傷がなく、くびきを負ったことがない赤い雌牛を、あなたのところに引いて来させなさい」。ここで用いられたのは雄牛ではなく、雌牛です。聖書の中で、性別はとても意義のあるものです。真理の証しのためのすべてのものには男性形が用いられますし、命の経験のためのすべてのものには女性形が用いられます。これは聖書を読む上で知っておかなければならない原則です。アブラハムは信仰によって義とされることを表し、サラは服従を表しています。信仰によって義とされることは、客観面、真理の面、証しの面のことであり、服従は主観面、命の面、経験の面のことです。全聖書の中で、教会がすべて女性形を用いて表されているのは、それが主観的なことであり、主が人の身の上においてなされた働きであるからです。このように、ここにおいて雄牛ではなく雌牛が用いられているのは、これがわたしたちの身の上における主の働きの一面を表しているからなのです。ですから赤い雌牛の働きが表しているのは、主観的なものです。
この赤い雌牛は殺され、指でその血をとり、会見の幕屋の前に向かって七度振りかけられます(民19:3-4)。これは神へささげることであり、罪の贖いのためです。この一頭の赤い雌牛を殺した後、持って行って焼かれます。牛の皮と肉と血と汚物はすべて焼かれます(民19:5)。その雌牛を焼いている時に、祭司は香柏の木とヒソプと緋色の撚り糸とを、火の中へと投げ入れます(民19:6)。この意味はなんでしょう?列王記上第4章33節には、ソロモンの知恵について述べられており、「彼はレバノンにある香柏から城壁に生えるヒソプに至るまで、樹木について論じた。」とあります。これは香柏からヒソプがすべての樹木を含んでいること、全世界を含んでいることを意味します。聖書の中ではイスラエルの全土を指す表現として「ダンからベエルシェバまで」という言葉が使われています(士師20:1、サムエル上3:20)。これはイスラエルの最北端に位置する地名の「ダン」と最南端に位置する地名の「ベエルシェバ」から来ています。ですから、「香柏の木とヒソプ」はすべてを含んでいるという意味です。「緋色の撚り糸」とはなんでしょう?原文によれば、「糸」という文字はなく、イザヤ書第1章18節で言っている「緋」と同じ文字です。イザヤ書第1章18節は言います、「たとえあなたの罪が緋のようであっても」。このことから、緋はわたしたちの罪を表します。ですから、香柏の木、ヒソプ、緋色の撚り糸と雌牛を一緒に焼くという意味は、全世界のすべての罪と、神にささげる一頭の牛とを一緒にして、共に焼くということです。これが主イエスが十字架上でわたしたちの全生涯の罪を担われたという根拠です。
この雌牛は焼き終えた後、どうするのでしょうか?9節はいいます、「そして、清い人がその雌牛の灰を集めて営所の外の清い所に置き、それをイスラエルの子たちの集団のため、汚れを除く水のために保存しておかなければならない。それは罪のためのささげ物である。」ここに雌牛の特別な点があります。この一頭の赤い雌牛を焼き、香柏の木とヒソプも焼き、緋の糸も焼き、その灰を集め、蓄えておきます。以後もしイスラエル人が汚れたものに触れて、神の御前に清くない者になったなら、身の清い人が流れの水を用いて赤い雌牛の灰を調合し、この清くない者の身に注ぎかけて、彼の汚れを除き去らなければなりません。言い換えれば、この灰の用途は、汚れを除き去るためであり、将来において清くなくなった時に用いるため前もって準備しておく「予備」としてのものです。
旧約において、罪人は神の御前に出て、いけにえをささげる必要がありました。しかし、もしある人がすでにいけにえをささげていて、再び汚れたものに触れるなら、彼は神の御前で清くない者であり、神と交わることができません。それでは、どうすればよいのでしょうか?この清くない者のために、赤い雌牛の灰を取って器に入れ、流れの水に加え、汚れを除く水を調合し、彼の身に注ぎかければ、彼の汚れは除き去られ、彼の罪は赦されるのです。赤い雌牛が焼かれるのは、彼が認識している過去の罪のためではなく、彼の将来におけるすべての汚れのためなのです。ですから、赤い雌牛が焼かれるのは、過去の罪のためではなく、将来の罪のためなのです。主の贖いのみわざの中には、わたしたちの将来のすべての汚れ、すべての罪のために、すでに準備があるのです。主の贖いにおいて、すべてがすでに完全に準備されました。
灰にはどんな意味があるのでしょうか?聖書において、灰は最も最終的な形を表すものです。牛でも、羊でも、焼かれた後の最後の形は灰です。灰は最も頼りになるものであり、灰は朽ち果てることのないものです。灰は消滅させることができません。灰は最後の段階のものです。赤い雌牛が焼かれて灰になることは、主の贖いに含まれている永遠に変わることのない効力を予表しています。
もしクリスチャンが不幸にもきよくないものに触れて、汚れたとしても、彼は再び主に自分のために死んでいただくように求めにいく必要はありません。ただその永遠に朽ちることのない灰の効力に信頼して、それを体に注ぎかければよいのです。言い換えれば、赤い雌牛の灰がわたしたちに告げていることは、十字架という過去のみわざは、今日用いるためのものであるということです。神に感謝します。主イエスの贖いは、わたしたちが一生涯、用いることのできるものです。彼の死は、わたしたちのすべての罪を担いました。
Ⅳ. 罪を告白する必要がある
わたしたちはこれまで、主のみわざを見てきました。神のみわざは完全で完璧です。では、わたしたちは何をすべきでしょうか?ヨハネの第一の手紙第1章9節は言います、「もし、わたしたちが自分の罪を告白するなら、神は信実で義であられるので、わたしたちの罪を赦し、すべての不義からわたしたちを清めてくださいます」。ここでの「わたしたち」は、信者を指しているのであって、罪人を指しているのではありません。信者が罪を犯したなら、必ず罪を告白する必要がありますし、そうしてこそ罪が赦されるのです。これが道です。箴言第28章13節は言います、「自分のそむきの罪を隠す者は成功しない。それを告白して、それを捨てる者はあわれみを受ける」。
例えば、うそをつくことは罪です。あなたがうそをついたなら、あなたはうそをついたこと、罪を犯したことを告白しなければなりません。あなたは「あれは少し言いすぎた」などと言って、罪を隠してはいけません。あなたは神の御前に出て、「わたしはうそをつくという罪を犯しました。」と告白しなければなりません。
罪を告白することの意味は、神の側に立って罪を罪定めすることです。ここに三者、すなわち、神、わたし、罪がいます。神と罪は両端にあり、わたしは中間にいます。罪を犯すとは、わたしと罪とが一緒になることであり、神を離れることです。わたしと罪が一緒にいながら、神と一緒にいる方法はありません。コロサイ人への手紙第1章21節は言います、「かつてあなたがたは神から離れていて、悪い行ないのために、あなたがたの思いの中で敵であった」。罪を告白することは、神の側に戻って、いま行なったことが罪であると告白することです。これは罪を罪定めすることであり、これによって神の側に戻ることができます。ですから、必ず光の中を歩み、罪に対して深い感覚を持ち、深く憎む人であってこそ、真に罪を告白することができるのです。罪に対して感覚がなく、罪を犯すこと、罪を告白することを日常茶飯事のように軽々しく行っている人は、ただ口先だけで告白しているのであって、それは罪を告白していることにはなりません。
わたしたちはヨハネの第一の手紙第一章の中の二つの「すべて」(7、9節)に注意する必要があります。「すべての罪」、「すべての不義」が、完全に赦され、完全に清められるのです。これは主がなさることです。主の十字架の死は、わたしたちのすべての罪を赦す効力があります。
Ⅴ. 御父と共にある弁護者
ヨハネの第一の手紙第2章1節は言います、「わたしの小さい子供たちよ、わたしがこれらの事を書き送るのは、あなたがたが罪を犯すことがないためです。」「これらの事」とは、わたしたちの罪がどのようにして神の約束と神のみわざによって赦され、清められたかを指して行っています。ヨハネがこれらを書いたのは、わたしたちが罪を犯さないようになるためです。赦されるのだからといって、罪を犯し続けることは神の愛を知らないのです。神の愛はわたしたちが罪を犯すことから救い出します。
その後、続けて言います、「もしだれかが罪を犯すなら、わたしたちには御父と共にある弁護者、義人イエス・キリストがあります」。主イエス・キリストは、ご自身の血に基づいてわたしたちの弁護者となられました。ですから、もしあなたが不注意に罪を犯してしまったとしても、決して失望しないでください。決して罪の中に横たわらないでください。決して罪の中にとどまり続けないでください。罪を犯したなら、まず第一に神の御前であなた自身の罪を告白すべきです。こうして、あなたと神との交わりが直ちに回復されるでしょう。
まとめ
どの兄弟姉妹も主の御前で罪を犯すべきではありません。もし不幸にも罪を犯したなら、まず第一にすぐに神の御前に出て罪を告白しなければなりません。決して引き延ばしてはいけません。すぐに罪を告白し、神に言いましょう、「わたしは罪を犯しました!わたしは罪人です!」罪を告白することは、わたしたち自身に対する裁きです。もしわたしたちが自分の罪を告白するなら、神は信実で義であられるので、わたしたちの罪を赦し、またすべての不義からわたしたちを清めてくださいます。
罪を犯してしまった後、神との交わりを回復する道はただ一つです。わたしたちが神の御前に行き、わたしたちの罪を認め、告白することです。わたしたちがこの次の道を歩む時に、おごり高ぶることがないように、いい加減にならないように、主を仰ぎ望みましょう。神がわたしたちをあわれんでくださり、わたしたちが一歩一歩前進できますように。
最後にやはり、クリスチャンは罪を犯すべきではないと言わなければなりません。罪を犯すことは、わたしたちに苦しみと損失を与えます。どうか神がわたしたちをあわれみ、わたしたちを守ってくださり、神との隔てのない交わりの中にとどまり続けさせ、絶えず前進させてくださいますように!
参考資料
ウォッチマン・ニー全集 第三期 第四十九巻 初信者を成就するメッセージ(二)第二十一編
出版元:日本福音書房
※ 本記事で引用している聖句に関して、明記していなければすべて回復訳2015からの引用です。
「オンライン聖書 回復訳」

2025-04-13 | 初信者成就シリーズ
(この記事は5,076文字で、10分で読み終えることができます。)
イエスは来て、彼らに語って言われた、「天においても地においても、いっさいの権威がわたしに与えられている。だから、行って、すべての諸国民を弟子とし、父と子と聖霊の名の中へと彼らをバプテスマして、わたしがあなたがたに命じておいたことを、すべて守るように教えなさい。見よ、わたしはこの時代の満了まで、日々あなたがたと共にいる」。 マタイによる福音書 28章18-20節
主は、弟子たちにすべての諸国民を弟子とし、命じておいていたことをすべて守るようにと告げました。すべての諸国民を弟子とすることは、人々をキリストへともたらすことです。人々をキリストにもたらすためには、いくつかのなすべきことや学ぶべきことがあります。それは二つに分けることができます。第一は、人のために神の御前に来ることです。第二は、神のために人の前に行くことです。
Ⅰ. 人のために神の御前に来る
A. 祈りは人々を主に導くための基本的な働きである
人々を主に導くための基本的な働きがあります。それは人に語りかける前に、まず神の御前で口を開いていなければならないということです。まず神に求め、それから人の前に行って語るのです。どれだけ熱心に人を救いにもたらそうとしても、神の御前で負担がなければ、その働きは成功しないことを知らなければなりません。神の御前で負担があってこそ、人の前で証しができるのです。
主イエスは言われました、「父がわたしに与えてくださる者はみな、わたしに来る」(ヨハネ6:37)。ですから第一のことはまず神に人を求めること、神が人を主イエスに与えてくださるよう、人を教会に与えてくださるよう要求することです。救われる人というのは、求めることによって、願い求めることによって神から出てきた人である必要があります。しかも人の心は最も取り扱いにくいものであって、容易に主に向きを変えさせることはできませんから、まず神の御前でよくよくこの人たちのために祈り、神があの強い者を縛り上げてくださるように求めるべきです(ルカ11:21-22)。必ず一人一人、神の御前に行き、よくよく祈るべきです。そうしてはじめて効果的に人を主にもたらすことができます。
人を主にもたらすことのできる人は、祈ることができる人です。もし祈りに確信がないなら、人々を主に導くことでも確信がないでしょう。ですから、祈りの学科において実際的な学びがあるべきです。
B. 記録ノートを準備する
よくよく人のために祈ろうとするなら、記録ノートを準備するのが良いでしょう。まず、すべきことは、神が救いたい人の名前を、神があなたの心に置いてくださるように求めることです。主がその人たちをあなたの心の中に置いてくださるなら、自然と心の中に負担が出てきて、何人かのために祈ることができます。名前を書くときに最も大切なことは、主があなたの心の中に置いてくださった名前を受け入れることです。勝手に名前を書き連ねるのではありません。
このノートはいくつかの項目に分けておくとよいでしょう。第一項目は番号、第二項目は日付、第三項目は名前です。第四項目は救われた日付です。もしあなたが主から負担を与えられ、いったん書いてしまったなら、その人が死ぬまで、祈り続けなければなりません。その人が救われていないなら、決して彼のための祈りをやめてはいけません。一人の兄弟は、ある人のために十八年間祈ってやっと救われました。これは、はっきりと言い切れないことですが、ある人は一年で救われ、ある人は二、三ヶ月で救われるでしょう。決して良い加減であってはなりません。必ず彼らは救われなければなりません。
C. 祈りの最大の妨げは罪である
祈りはテストです。あなたの神の御前での霊的な状態がどうであるかをテストします。もしあなたの霊的な状態が正しく、正常なら、これらの人は一人一人と救われるでしょう。主の御前で求め続けていれば、何日か後、あるいは半年後、一人、二人が救われるでしょう。もしあまりにも長い時間がたっても祈りが答えられないなら、きっとあなたには神の御前で病があるのですから、神の御前に行って、どこに対処すべき問題があるかを光で照らされるように求めなければなりません。
祈りの最大の妨げは罪です。わたしたちは神の御前で聖い生活をすることを学ぶべきです。罪とわかっているものはすべて拒まなければなりません。祈りの詳細については「祈りが答えられるための五つの条件と実践ガイド – 叶えられる祈り – 初信者シリーズ 8 」をご覧ください。
D. 祈れる人となるように求める
兄弟姉妹は、神の御前で祈れる人に、力のある人になるように求める強い心が必要です。ある人は神の御前に力がありますが、ある人は神の御前に力がありません。ある人の神の御前での言葉は神に聞かれますが、ある人たちの言葉は聞かれません。神の御前で力ある者となることは、何を意味するのでしょうか?それはその人が祈る時、神がその人の祈りを聞かれるということです。それはまるで、神が喜んでその人の影響を受けられるかのようです。わたちたちの内側には、祈りがいつも神に聞かれるように願い求める気持ちが必要です。あなたが祈れば神はいつも聞かれるなら、これ以上にすばらしいことはありません。わたしたちは神に求めて、「わたしがあなたの御前で何かを求める時、あなたが喜んで聞いてくださいますように」と言う必要があります。
もし、神があなたの祈りを聞いてくださらないなら、自分と、あるいは神と交渉しなければなりません。祈りが答えられるには、常に交渉が必要です。祈りが答えられないのは病があるからです。こういうわけで祈りのノートが必要となってくるのです。このノートは、あなたの祈りが答えられたかどうかを知らせてくれるものです。多くの人は、祈りを記録していないため、答えられたかどうか全く知りません。ですから、わたしたちは祈りのためにノートを準備しなければなりません。
E. 日々祈る
あなたは周りの人たちのために祈らなければなりません。まず神に、一人二人を特別にあなたの心の中に置いてくださるよう求めなければなりません。
毎日一定の時間を取り出して、とりなしの働きをする必要があります。一時間でも、三十分でも、十五分でも構いませんが、一定の時間を取り出さなければなりません。もし祈るための一定の時間がなければ、ついには祈らなくなるでしょう。ですから、祈りの時間を定め、祈らなければなりません。これは訓練される必要があります。
Ⅱ. 神のために人の前に行く
人のために神の御前に来るだけでは十分ではありません。さらに神のために人の前に行き、神がどのような方であるかを語らなければなりません。人に対して語る時、特に注意すべきことがいくつかあります。
A. 決して無意味な議論をしない
第一に、決して無意味な議論をしてはなりません。絶対に議論してはいけないとは言いません。使徒行伝にはいくつかの議論が記されていて、パウロでさえ議論しているからです(使徒17:2,17、18:4,19)。しかし、無意味な議論で人を得ることはできません。なぜなら、議論はしばしば人を去らせてしまうからです。あなたは議論の言葉を少なくし、証しの言葉を多くすべきです。主イエスを信じてどんな喜びや平安を得たかなどを語ればよいのです。証しに議論の余地はありません。
B. 事実をつかむ
人々を主に導くコツは、理屈ではなく事実に注意することです。自分の救われた時はどうであったかを考えてみてください。あなたは教えがよくわかったから信じたのではないでしょう。人々を主に導くコツは、事実をつかむことにあります。ですから、単純な人は人々を主に導くことができますが、教えをうまく語れる人は人々を主に導くことができるとは限らないのです。
かつて一人の老人がいました。彼は救われていませんでしたが、礼拝堂に行くのは良い習慣であると思っていたので、毎週自分も行き、家族にも行くように言っていました。しかし、彼が帰ってくると、すぐに短気を起こして、口汚い言葉の限りを尽くすのです。ある日、娘が里帰りしてきました。彼女は主にある姉妹であり、小さな娘を連れて帰ってきました。その老人はこの小さい孫も連れて礼拝堂に行きました。礼拝堂から出てきた時、孫娘は祖父を見てこのように言いました、「おじいちゃん、イエスを信じているの?」。その老人は、「子供は余計なことを言うものではない」と言いましたが、しばらく歩いていくと、孫娘はまた「おじいちゃんはイエスを信じていないみたい」と言いました。そしてまた、「おじいちゃん、どうしてイエスを信じないの?」と言いました。この子は一つの事実を見いだしたのです。孫娘に質問されてから老人は柔らかくなり、ついに主を受け入れたのです。
福音を伝えるには技術が必要です。神の道を知ってはじめて福音を伝えることができます。事実の言葉は人の心に触れるのです。
C. 誠実で熱心な態度を持つ
教理を多く語る必要はありません。さらに多くの事実を告げる必要があります。それと同時に、その態度は誠実で熱心でなければなりません。軽率な態度であってはなりません。わたしたちは冗談を言うことによって霊的な力をすべて失ってしまいます。これは地上で最も厳粛なことであることを、人々に見せる必要があります。
D. 時が良くても悪くても語る
これまで、まず人のために神の御前に行って祈り、それから人に話すということを述べてきました。しかし、これは祈らなければ語ってはいけないということではありません。初めて会った人にも語らなければなりません。つまり機会を捕らえること、時が良くても語り、時が悪くても語ることです。わたしたちが少しでも不注意であれば、一つの魂を得損ねてしまうでしょう。
E. 注意深く研究する必要がある
あなたが一人の人を主に導いた時は、いつでもさらにそのケースを注意深く研究しなければなりません。ちょうど医者がいろいろな病人の症状を研究するのと同じです。この世では、医学を学んでいないのに医者になれる人はいません。同様に、人々を主に導くことを学ばないで、人々を主に導けるようになる人はいません。わたしたちは必ず研究しなければなりません。なぜその人は受け入れることができたのか?なぜこの一言で彼は受け入れたのか?なぜその人はその言葉を聞いても受け入れなかったのか?わたしたちは、人に福音を語るために真剣にならなければなりません。
Ⅲ. 福音はわたしたちの使命である
イエスは来て、彼らに語って言われた、「天においても地においても、いっさいの権威がわたしに与えられている。だから、行って、すべての諸国民を弟子とし、父と子と聖霊の名の中へと彼らをバプテスマして、わたしがあなたがたに命じておいたことを、すべて守るように教えなさい。見よ、わたしはこの時代の満了まで、日々あなたがたと共にいる」。 マタイによる福音書 28章18-20節
福音はわたしたちの使命です。現在、神がわたしたちに願っていることは、すべての聖徒たちが機能することです。福音は主からの命令です。神はすべての聖徒たちが与えられた一タラントを活用することを願っておられます。わたしたちは兄弟姉妹と組み合わされて、福音する必要があります。それは人を得るためであり、またキリストのからだを建造するためです。
この記事では、人々をキリストへと導くために大きく二つのことを交わりました。第一は、人のために神の御前に来ることであり、第二は、神のために人の前に行くことです。わたしたちはまず、神の御前に出なければなりません。そして、神から負担を与えられた人のために日々祈る必要があります。この継続した祈りの積み重ねのために祈りのノートを作る必要があります。
次に神のために人の前に行きます。人に福音をする時の注意点は、無意味な議論をしないこと、事実をつかむこと、時が良くても悪くても語り続けること、そして、福音について研究することです。福音はわたしたちに与えられた使命です。
参考資料
ウォッチマン・ニー全集 第三期 第四十九巻 初信者を成就するメッセージ(二)第十九編
出版元:日本福音書房
※ 本記事で引用している聖句に関して、明記していなければすべて回復訳2015からの引用です。
「オンライン聖書 回復訳」

2025-04-06 | 初信者成就シリーズ
(この記事は8,799文字で、18分で読み終えることができます。)
主イエスがこの世を去られる前夜、弟子たちとともに食卓を囲みました(マタイ26:26-28)。その食卓で主が設けられた『晩餐』は、教会にとって特別な意味があります。なぜこの晩餐が設立されたのか。また主の晩餐はどのような意義を持つのか。それはただの儀式ではなく、深淵な霊的意義を含んでいます。
まず初めに「パンさきの意義」についての結論を述べます。パンさきには「主の晩餐」と「主の食卓」という二つの面があります。「主の晩餐」は、主を記念し、主の死を告げ知らせるためです。「主の食卓」は、わたしたち信者がキリストの中で「一」であり、互いに交わりを持っていることを証しすることです。このパンさきは、主の為されたみわざを思い起こし、また主の再来を待ち望みます。わたしたち信者は、キリストの中で「一」であり、交わりを持っていることを深く知るのです。
この記事では、このパンさきについて詳しく見ていきたいと思います。
Ⅰ. 主の晩餐の設立
教会には神の子たちが出席すべき晩餐があります。この晩餐は、主イエスがこの地上で生きておられた最後の夜に設けられたものであり、その翌日に彼は十字架に釘付けられました。これは主イエスが地上で生きておられた最後の夜に食された最後の食事です。
この最後の食事とはどのようなものなのでしょう?これには一つの物語があります。ユダヤ人には過越の祭りと呼ばれる祭りがあって、エジプトで奴隷となっていた時に神が彼らを救われたことを記念しました。神がユダヤ人を救われた方法はこうです。神は、おのおのその父の家ごとに小羊を一家族に一頭取って、正月の十四日の夕暮れにこの小羊を殺し、その血を門柱とそのかもいに塗ること、また、その夜はこの小羊の肉を種入れぬパンと苦菜を添えて食べるように命じられました。ユダヤ人がエジプトから出てきた後、毎年この祭りを守って記念するようにと神は命じられました(出エジ12:1-28)。ですから、ユダヤ人にとって過越の祭りは、救われたことを思い起こすことです。
主イエスがこの世を離れようとしていたその夜は、過越の小羊を食べる時でした。主イエスが弟子たちと過越の小羊を食べた直後、主はご自身の晩餐を設けられました。主はここで、ユダヤ人が過越の小羊を食べるのと同じように、わたしたちが彼の晩餐を食べるべきであることを示されたのです。
この二つの事柄を対比させて見てみましょう。イスラエル人は救われてエジプトを脱出したので過越の祭りを守ります。神の子たちは救われてこの世の罪悪から離れたので主の晩餐を食べるのです。イスラエル人には小羊があり、神の子たちであるわたしたちにも小羊があるのです。この小羊とは主イエスです(ヨハネ1:29,36)。今日わたしたちはすでにこの世の罪悪から離れ、サタンの支配から離れ、完全に神に帰されました。ですから、ユダヤ人が過越の小羊を食べるのと同様に、わたしたちは主の晩餐を食べるのです。
彼らが食事をしていた時、イエスはパンを取り、それを祝福してさき、弟子たちに与えて言われた、「取って食べなさい。これはわたしの体である」。また杯を取り、感謝をささげて、それを彼らに与えて言われた、「みな、それから飲みなさい。これは、多くの人に罪の赦しを得させるために、注ぎ出されるわたしの契約の血である(マタイ26:26-28)。これが主の設けられた晩餐です。
晩餐とは、一日の仕事がすっかり終わって、家族が一緒にくつろいで取る食事のことです。それは朝食や昼食のような慌ただしいものではなく、くつろいで気楽に食事をし、安息の味わいに満ちているものです。神の子たちが晩餐にあずかる時も、このような雰囲気であるべきです。その晩餐では、忙しくするのでもなく、あれやこれやと考えるのでもなく、ただ神の家の中で安息を享受するのです。
主イエスが晩餐を設けられたのは過越の祭りの時でしたから、用いられたのは種の入っていないパン(出エジ12:15)であり、種を入れてふくらませたパンではありません。またマタイによる福音書第26章、マルコによる福音書第14章、ルカによる福音書第22章では、「ぶどうからできたもの」と言っています。ですから、パンをさく時には、ぶどう酒を使っても、ぶどうジュースを使っても良いのです。
Ⅱ. 主の晩餐の意義
なぜ主はわたしたちに晩餐を行うように言われたのでしょう?それは大きく二つの理由があります。一つ目は「主を記念するため」であり、二つ目は「主の死を告げ知らせるため」です。
A. 主を記念する
コリント人への第一の手紙第11章24節で主は、「わたしの記念にこれを行いなさい」と言われました。ですから、晩餐は第一に、主を記念するためのものです。主は、わたしたち人がいとも簡単に彼を忘れてしまうことを知っておられます。わたしたちの得た恵みはこんなにも大きく、その贖いはこんなにもすばらしいものですが、人はすぐに忘れてしまうのです。ですから、主は特に言われたのです、「わたしの記念にこれを行いなさい」。
主がわたしたちに彼を記念するように言われたのは、わたしたちがただ忘れてしまいやすいからだけでなく、わたしたちが彼を記念することを主ご自身が必要としておられるからです。言い換えれば、主は私たちに忘れてほしくないのです。彼は偉大でわたしたちをはるかに超えています。わたしたちが記念しようとしまいと、別になんでもないと考えるかも知れません。しかし、主の言葉は「わたしの記念にこれを行いなさい」です。これは、主がご自身を低くされていることを見せています。すべてを超越しておられる方がわたしたちの記念を受けてくださるのです。これはわたしたちに対する愛の要求です。もしわたしたちが主を常に記念することをせず、主の贖いも自分の前に置かないとしたら、わたしたちは容易にこの世の罪悪と一つとなってしまい、容易に神の子たちとの間に争いが生じるでしょう。
あなたが主を記念する時、この世の罪の力があなたの身に影響を及ぼし続けることができなくなるという大きな益があります。主日ごとに主を記念することによって、どのように主を受け入れたか、どのように主に受け入れられたか、どのように主が自分に代わって死なれたかを思い出すなら、もはやこの世の罪と一つになることはできなくなるでしょう。これが、パンをさいて主を記念することの一つの益です。また、主を記念することは、神の子たちが争うことができないようにし、区別したり差別したりすることができないようにします。あなたが自分はどのように恵みを受けて救われたかを記念している時、別の兄弟もそこでどのように恵みを受けて救われたかを記念しているとしたら、彼を愛さずにはいられません。あなたが、主イエスは自分の千万の罪をすべて赦してくださったことを思う時、別の姉妹が入ってきて、彼女も血による贖いを受けているとしたら、彼女を赦さないということは不可能です。主の晩餐の食卓に来る時、すべての問題は消え去ります。なぜなら、主を記念することは、あなたがいかに救われたか、いかに赦されたかを記念することだからです。
自分の多くの罪を主はすべて赦してくださったのに、なお兄弟姉妹と争い合うことなど、あってはなりません。集会で主を記念する時はいつでも、主はわたしたちにもう一度、彼の愛を学ばせ、十字架のみわざを学ばせ、救われた人はみな主が愛しておられる人であることを学ばせられるのです。主はわたしたちを愛し、わたしたちのためにご自身を捨てられました。主はあなたのために、またすべて彼のものである人たちのためにも、ご自分を捨てられたのです。
多くの人が怠惰になって実を結ばないのは、以前の罪がすでに清められていることを忘れてしまったからです(Ⅱペテロ1:8-9)。ですから、主はわたしたちにご自身を記念し、愛するようにと言われるのです。この杯は彼の血によって立てられた新しい契約であり、わたしたちのために流されたことを記念するものです。このパンは彼の体であり、わたしたちのために捨てられたことを記念するものです。これがパンさきの第一の重要点です。
B. 主の死を告げ知らせる
主の晩餐にはもう一つの意義があります。コリント人への第一の手紙第11章26節は言います、「ですから、あなたがたがこのパンを食べ、その杯を飲むたびに、主が来られるまで、主の死を告げ知らせるのです」。あなたがパンを食べ、杯を飲むことは、主の死を告げ知らせることなのです。「告げ知らせる」とは、人々に知らせるという意味です。
このパンと杯は、どのようにして主の死を告げ知らせるのでしょうか?血は本来、肉の中にあるものです。その血と肉が分かれてしまえば、それは死を意味します。この杯の中にぶどう酒を見る時、血を見ます。このパンを見る時、肉を見ます。主の血は一方にあり、主の肉がもう一方にあります。血と肉とが分かれてしまっています。これは主の死を表しているのです。この集会では、「わたしたちの主はあなたに代わって死なれました」と言う必要はありません。血が肉の中にないことを見るだけで、ここに死があることがわかります。
このパンはひかれた穀物です。この杯に中のものは搾られたぶどうです。このパンを見ると、そこにはすでにひかれた穀物があり、この杯を見ると、そこにはすでに搾られたぶどうがあります。ここに「死」があります。小麦の粒はひかれなければ一粒のままであって、パンにはなりません。一房のぶどうが搾られなければ、酒(液)もありません。ですから、わたしたちがこのひかれた穀物を食べ、搾られたぶどうを飲む時、これは主の死を告げ知らせることなのです。
あなたの両親、子供たち、親族は主を知らないかもしれませんが、もしあなたが彼らをパンさきの集会に連れて来たら、彼らは初めてパンさきを見て質問するでしょう。「これは一体どういうことですか?パンをさくとはどんな意味ですか?杯を飲むとはどんな意味ですか?」。あなたは言います、「もしこの杯の中のものが血であり、このパンが肉であるとしたら、これはどういうことでしょうか?」。彼らは「これは死です」と答えるでしょう。わたしたちは人に指し示して、ここに置かれているのは主の死であると見せることができます。ですから、出て行って口を使って福音を伝えるだけでなく、集会所で福音を語るだけでなく、主の晩餐も福音を伝えることなのです。
人から見れば、主イエスはもはや地上にはおられませんが、十字架のしるし、すなわちパンと杯が存在し続けています。毎回パンと杯を見る時に、主の十字架上の死を見ます。この十字架のしるしは、主がわたしたちに代わって死なれたことが必ず記憶されるべきであることを示しています。
「ですから、あなたがたがこのパンを食べ、その杯を飲むたびに、主が来られるまで、主の死を告げ知らせるのです」。主イエスは再来しようとしておられます。この言葉は晩餐と一緒にすると特別な意味があります。晩餐は一日の最後の食事です。わたしたちは毎週この晩餐にあずかります。教会は週ごとに同じ晩餐にあずかります。すでに二千年近くもたちましたが、この晩餐はまだ過ぎ去ってはいません。わたしたちは、この晩餐にあずかり続けます。ずっと待って、ある日主が来られる時、もはやこの晩餐にはあずからないでしょう。顔を合わせてわたしたちの主を見る時、晩餐は過ぎ去るでしょう。わたしたちは主を見たなら、もはや主を記念する必要がなくなります。ですから、晩餐の第一の意義は「主を記念すること」であり、第二の意義は「主の死を告げ知らせる」ということです。主の晩餐は、わたしたちが主ご自身を記念するためです。人が主ご自身を記念すれば、自然に主の死も記念するようになります。主の死を記念するなら、自然に王国を待ち望むでしょう。ある日、主は来られます。
Ⅲ. 主の食卓の意義
コリント人への第一の手紙第10章では、別の言葉を用いてパンさきを説明しています。それは晩餐ではなく、「食卓」であると言っています。主が最後の夜に設けられた晩餐において、主を記念し、主の死を告げ知らせ、主の再来を待つのですが、これは一面にすぎません。教会のパンさきにはもう一面があって、それはコリント人への第一の手紙第10章21節で言われている「主の食卓」です。
主の食卓の意義は、コリント人への第一の手紙第10章16節と17節ではっきりと語られています、「わたしたちが祝福する祝福の杯、それはキリストの血の交わりではありませんか?わたしたちがさくパン、それはキリストの体の交わりではありませんか?一つパンであるからには、わたしたちは数が多くても一つからだなのです。それは、わたしたちがみなこの一つパンにあずかるからです」。ここにも二つの意義があります。一つは「交わり」であり、もう一つは「一」です。
A. 交わり
主の食卓の第一の意義は交わりです。「わたしたちが祝福する祝福の杯、それはキリストの血の交わりではありませんか?」。わたしたちはみな、主の杯から飲みます。これが交わりです。コリント人への第一の手紙第10章は信者と信者のお互いの関係を言っています。晩餐はわたしたちが主を記念することを語り、食卓はわたしたちの互いの交わりです。食卓については、「わたしたちが祝福する祝福の杯、それはキリストの血の交わりではありませんか?」と言っています。ここでの重要点は、キリストの血にあずかることではなく、キリストの血の交わりにあります。
「わたしたちが祝福する祝福の杯」の「杯」は単数です。マタイによる福音書第26章27節で言われている「杯」も単数です。原文どおり直訳すれば、「また杯を取り、感謝をささげて、それを彼らに与えて言われた、『みな、それから飲みなさい』」となるべきです。ですから、杯の数を多くすることには賛成しません。なぜなら、意味を変えてしまうからです。一つの杯から共にあずかること、これが交わりの意味です。もしお互いが親密でなければ、同じ一つの杯からあなたが一口、彼が一口飲むことはできないでしょう。神の子たちは共に一つの杯から飲みます。一つの杯からあなたが一口、彼が一口、これほど多くの人たちがみなこの一つの杯から飲むのです。それが交わりです。
B. 一
第二の意義は「一」です。「わたしたちがさくパン、それはキリストの体の交わりではありませんか?一つパンであるからには、わたしたちは数が多くても一つからだなのです。それは、わたしたちがみなこの一つパンにあずかるからです」。ここでは、神の子たちが一つになっているのを見ます。コリント人への第一の手紙第11章で言われているパンと第10章で言われているパンには違う意味があります。第11章では、主はパンについて「これは、あなたがたのために与えるわたしの体である」(Ⅰコリント11:24)と言われました。これは主イエスの肉体を指して言われたのです。第10章では、パンは教会を指しています。「わたしたちは数が多くても一つからだなのです」(Ⅰコリント10:17)。ですから、わたしたちはパンであり、このパンは教会です。
すべての神の子たちは、このパンが一つパンであるように一つです。わたしたちにはただ一つのパンがあるだけです。キリストはパンのようにもともと一つです。神はキリストを少しあなたに分け与え、また彼にも少し分け与えられたので、ひとりのキリストは今や多くの人の心の中に住んでおられます。神の子たちがパンをさく時には、ただ主を記念するだけでなく、主の死を告げ知らせるだけでもなく、また神のすべての子たちと交わりを持つだけでもなく、神のすべての子たちが一であることを承認するのです。この一つのパンは神の教会が一であることを表しているのです。
主の食卓の基本的な要素はパンです。このパンは、大きく言えばすべての神の子たちを代表していますし、小さく言えば一つの地方のすべての神の子たちを代表しています。もし何人かの神の子たちが共に集まり、ただその何人かだけを見るなら、そのパンはその何人かだけを含むもので小さすぎて、十分ではありません。一つのパンは、一つの地方のすべての神の子たちを表し、一つの地方の教会を代表しているべきです。またそれだけでなく、この一つパンはこの地上にいるすべての神の子たちを含むものです。わたしたちは、このパンがすべての子たちの一を表していることを見なければなりません。もし一つの単独の教会を設立しようとするなら、そのパンはあまりにも小さすぎて、教会を代表することはできません。
もしわたしたちと共にパンをさいたことのない兄弟が主の食卓の前に来るとします。彼は主と結合していますから、このパンの中にあります。わたしたちは彼を受け入れるでしょうか、それとも受け入れないでしょうか?覚えておかなければならないことは、わたしたちは主人ではなく、接待役に過ぎないということです。食卓は主のものであって、わたしたちのものではありません。わたしたちが主に属する人にパンをさかせないと言うことはできません。この食卓は主のものですから、受け入れるかどうかの権威は主にあり、わたしたちにはありません。わたしたちが拒むことのできる人は、罪の中にとどまって、そこから出てこようとしない人です。なぜなら、彼は主との交わりを断ってしまったのですから、わたしたちも彼との交わりを断つのです。パンさきに受け入れることでは、注意深く判断し、いい加減ではなく、主のみこころに合うようにしなければなりません。
Ⅳ. パンさきの集会で注意すべきこと
最後に二つのことを交わりたいと思います。一つはパンさきの集会とはどのようなものであるか。もう一つは、主を記念する時に、わたしたちはふさわしくなければならないということです。
A. パンさき集会
パンさきの集会では顧みなければならない特別な状況があります。それは、わたしたちは主の血で洗われた人であって、血で洗ってくださるように求める人ではないことです。わたしたちは主の命を得た人であって、命をくださるように求める人ではありません。ですから、この集会ではただ祝福があるのです。主は渡された夜に、「パンを取り、それを祝福して・・・また杯を取り、感謝をささげて」(マタイ26:26-27)。主は祝福し感謝をされただけです。弟子たちとパンをさき終わってから、なおも賛美を歌われました(マタイ26:30)。ですから、この集会の正常な雰囲気は、祝福と感謝と賛美なのです。
パンさきは週に一度です。主は晩餐を設けられた時、「あなたがたは常にこれを行いなさい」(原文には常にの意味があります)と言われました。初期の教会では、週の初めの日にパンをさきました(使徒20:7)。わたしたちの主は死んだだけでなく、復活されました。わたしたちは復活の中で主を記念するのです。
B. ふさわしい
主を記念する時、わたしたちは「ふさわしく」なる必要があります。コリント人への第一の手紙第11章27節から29節は言います、「こういうわけで、だれでも、ふさわしくないままで主のパンを食べ、主の杯を飲む者は、主の体と血に対して罪を犯すのです。人は自分自身を吟味して、それから、そのパンを食べ、その杯から飲みなさい。なぜなら、食べ飲みする者が、その体をわきまえないのであれば、自分自身に対する裁きを、食べ飲みすることになるからです」。食べるときに最も重要なことは、ふさわしいことです。これは人がふさわしいかと言うのではなく、その態度がふさわしいかどうかです。もし一人の人が主のものであるなら、問題ではありません。しかし、もし主の人でないなら、パンをさくことはできません。ですから、ふさわしいかどうかの問題は、人の問題ではなく、態度が正しいかどうかの問題です。
また、わたしたちは兄弟姉妹との間に争いを持ったまま、パンと杯にあずかるべきではありません。パンと杯を食べ飲みすることは受け入れることです。もし、あなたが兄弟姉妹に対して怒っており、赦していないのであれば、パンと杯にあずかるべきではありません。このパンと杯はすべての兄弟姉妹のためのものです。あなたが赦されているように彼らも赦されているのです。わたしたちの態度が正しいかどうかをよくよく吟味する必要があります。
まとめ
パンさきには二つの面があります。一つは「主の晩餐」であり、もう一つは「主の食卓」です。「主の晩餐」は主を記念すること、主の死を告げ知らせるためです。「主の食卓」は、わたしたち信者が互いに交わりを持つことであり、キリストのからだの一を証しすることです。
「ですから、あなたがたがこのパンを食べ、その杯を飲むたびに、主が来られるまで、主の死を告げ知らせるのです」(Ⅰコリント11:26)。この御言葉でパウロは、「主が来られるまで」と言われました。わたしたちは聖書の御言葉にしたがって、「主が来られるまで」パンをさき続ける必要があります。パンさきはただの儀式ではなく、霊的実際に満ちているものなのです。わたしたちは、兄弟姉妹と共にパンと杯にあずかる時、この上ない喜びの中にあることを証することができます。
参考資料
ウォッチマン・ニー全集 第三期 第四十八巻 初信者を成就するメッセージ(一)第十七編
出版元:日本福音書房
※ 本記事で引用している聖句に関して、明記していなければすべて回復訳2015からの引用です。
「オンライン聖書 回復訳」
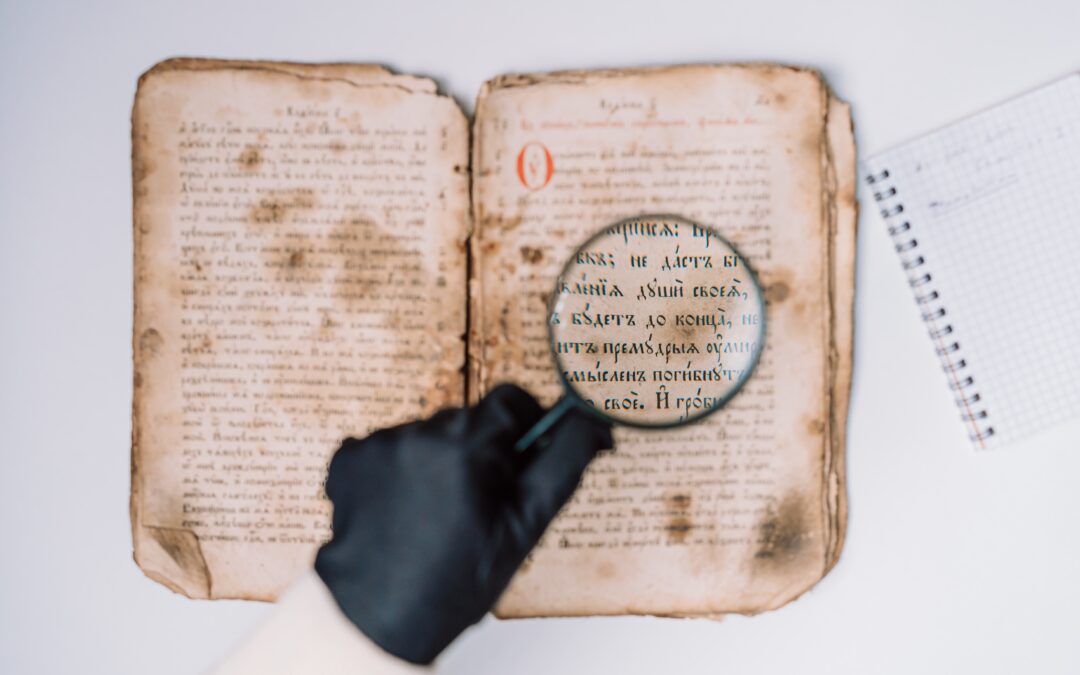
2025-03-30 | 初信者成就シリーズ
十二使徒の教え(紀元75-90年)
主日に関しては、「十二使徒の教え」(聖書以外の最初の教会の書物であり、およそ紀元七十五年から九十年の間に書かれたものであり、少なくとも啓示録と同時代のものである)という書物の中に、以下のような言葉があります、「主日ごとに、あなたがたは共に集まって、自分の罪を告白した後、パンをさき、感謝をささげなければなりません。そうすれば、あなたがたがささげるささげ物は清められます」。これは、信者が主日の集会において、第一世紀の終わりごろにこのようにしていたことをはっきりと見せています。
イグナチウス(紀元100年)
使徒ヨハネに一人の弟子がおり、その名をイグナチウスと言い、彼は紀元三十年に生まれ、紀元百七年に殉教しました。彼は紀元百年の時、一通の手紙をマイニシア地方の者に書き送りました。この一通の手紙の第九章の中で、彼ははっきりと言っています、「あなたがたは昔の教える人(ユダヤ教の人たちを指す)にしたがって、第七日の安息日を守ることは、もはや今日すべきではありません。主日を守るべきです。なぜなら、その日にわたしたちの命は彼と共に発芽したからです」。これもまたはっきりと、初期の教会が安息日を守っていたのではなく、主日を守っていたことを見せています。
バルナバ(紀元120年)
およそ紀元百二十年にバルナバ(聖書に出てくるバルナバではない)が書いた一通の手紙の第十五章に次の一句があります、「わたしたちは喜んで第八日、つまり主イエスが死から復活された日を守ります」。
エスティノス(紀元138年)
さらにもう一人の教父がおり、人は彼のことを殉教者エスティノスと呼び、教父たちの中ではかなり有名な人です。彼は紀元百年に生まれ、紀元百六十五年に殉教しました。紀元百三十八年の時、彼は「弁証論」という書物を書きました。その書物の中で彼は言っています「日曜日つまり週の初めの日に、すべて町に住んでいる者とその町以外に住んでいる者は共に集まり、みなで使徒の伝記と預言者の著作を読みます。時間が許す限り、読めるだけ読みます。読み終わったら、数句の教える言葉があれば、導く兄弟が、それらの良い事に習うようにとみなに勧めをします。後ほどわたしたち全体は立ち上がって祈り、祈り終わったらパンとぶどう酒を持ってきて、導く人が祈りと感謝をささげ、全員が心を一つにして「アーメン」と言います。富んでいる人も、心から喜んでささげる人も、各自はその感謝にふさわしい額をささげます。それを集めて処理する人に託し、その人が孤児や寡婦、病人、必要のある人、捕らわれている人、わたしたちの間で集会している人を顧みます。言い換えれば、必要のあるすべての人を顧みるのです。日曜日はわたしたちの普通の集会の日です。なぜなら、イエス・キリスト、わたしたちの救い主がこの日に死から復活されたからです。主は土曜日の前日に釘づけられ、土曜日の翌日、つまり日曜日に彼の使徒や弟子たちに現れ、彼らにこの事を教えられました。今日この事をあなたがたに書き送るので、それを考慮するようにしてください」。さらにもう一箇所で彼は言っています、「わたしたちは罪と過ちの中から、わたしたちの主イエス・キリストを通して割礼を受けました。彼は週の初めの日に、死から復活されました。ですから、この日はすべての日の中で主要な日、第一日となったのです」。
メリト(紀元170年)
紀元百七十年、サルデスに在る教会に、メリトと呼ばれた教父がいました。彼の書いた本の中に光のような一句があります、「わたしたちは今日、主の復活の日を過ごしています。この時わたしたちは多くの手紙を読みます」。
クレメンス(紀元194年)
紀元百九十四年、アレクサンドリア市にクレメンスという有名な教父がいました。彼は炎のように言いました、「第七日は今日、働きの日となっています。それはまた普通の働きの日でもあります」。続けて彼はまた言っています、「わたしたちは主日を守るべきです」。
テルトゥリアヌス(紀元200年)
紀元二百年、教父テルトゥリアヌスは言いました、「主日に、わたしたちは特に喜びに満たされます。わたしたちはこの日を、すなわち主の復活の日を守ります。妨げもなく、心配事もありません」。そのころすでに、主日を守ることは太陽を礼拝することであると批判する人がいたので、テルトゥリアヌスは彼らに答えて言いました、「わたしたちは主日に喜びます。わたしたちは太陽を礼拝しているのではありません。わたしたちは、怠けて土曜日に宴会しているような人たちとは異なります」。
オリゲネス
オリゲネスは、教父たちの中でも有名な一人ですが、彼はアレクサンドリアの有名な神学者です。彼は、「主日を守ることは完全なクリスチャンであることのしるしです」と言っています。
週の初めの日は安息日ではない
ある人は、古代の信者たちは安息日を守っていたのであり、第四世紀にコンスタンティヌスが週の初めの日を守るように改めさせたのである、と言います。これは事実に合いません。コンスタンティヌスは、この日を改めたのではなく、この事実を認めたのにすぎません。というのは、教会はすでに長い間、主日を守ってきていたからです。紀元三百十三年の前までは、クリスチャンは迫害を受けました。紀元三百十三年の後、コンスタンティヌスはローマを支配し、ミラノ地方で一つの詔書を発布し、クリスチャンを迫害することを禁じました。紀元三百二十一年、コンスタンティヌスは第二の詔書を発布し、言いました、「主日には、役人も一般民衆も、町に住む者はみな休むべきであり、すべての仕事は停止すべきである」。
この詔書の中でコンスタンティヌスは、初めから終わりまで安息日には全く触れておらず、ただ週の初めの日が教会の日であることを認めただけでした。
以上の資料の中から、主日を守ることは、使徒と教会の教父たちの時から始まり、これが各時代の実行であったことを知ることができます。
参考資料
ウォッチマン・ニー全集 第三期 第四十八巻 初信者を成就するメッセージ(一)第十四編
出版元:日本福音書房

2025-03-30 | 初信者成就シリーズ
(この記事は5,924文字で、12分で読み終えることができます。)
現代の多くのクリスチャンは、日曜日が「安息日」であると考えています。しかし、それは誤った聖書解釈です。この誤解は、聖書に啓示されている真理を曇らせてしまいます。この記事では、まず聖書の啓示に基づき、安息日についての考えを深めましょう。そして、「安息日」と「主日」との違いを明らかにし、私たちがどのような立場で歩むべきかを見ていきます。もし、あなたがまだ日曜日は「安息日」であると考え、それを守っているなら、あなたは恵みの下にではなく律法の下に歩んでいるかもしれません。聖書の中で神が私たちに与えられた真の安息とは何か、主日とは何かを、一緒に見ていきましょう
神は六日かかって天地万物を造り終え、第七日にはすべてのわざをやめて安息されました。その約2,500年の後、神は十戒を与えられました(出エジ20:1-17)。その中の第四の戒めは、人に安息日を記念させるものであり、神のみわざを記念させるものです。この安息日の記念は、神が世界を回復した時、六日間で回復を終え、第七日に安息されたことを、人に振り返って見させるものです。ですから、第七日はもともと神が安息された日です。ここから約2,500年余り経ってから、神はこの第七日の安息日を人に与えて、人もまた安息するようにさせたのです。
旧約の事柄は、すべてきたるべき素晴らしい事柄の影にすぎません(ヘブル10:1)。神が人に安息日を与えられたことも、旧約のその他の多くの予表と同様に、霊的な意義があります。神は第六日に人を造り、第七日に安息されたのですから、人は造られるとすぐに働いたのではなく、まず神の安息の中へと入り込みました。人はまず安息し、その後はじめて働いたのです。これが福音の原則です。ですから、安息日は福音の予表です。安息が働きの前にあること、これが福音です。
安息日の意義は、人が働かずにただ神の安息に入り込むことです。人が神の安息に入り込むとは、人が自らの働きをやめ、神のみわざを受け入れることです。人が安息日を犯すことは、大きな事柄ではないかのように見えますが、神の真理から言えば、それは実に大きな事柄です。人はまず福音を受け入れるべきであり、そうしてこそ行うことができます。人が安息日を犯すとは、自分自身で働くことができ、自分自身で行うことができるということであり、つまり、神のみわざを必要としないことの表示です。安息日を守ることは、何もしないということではなく、人が神の安息の中で安息し、神のみわざを受け入れることです。これが旧約においての安息日がわたしたちに見せていることです。
Ⅰ. 主日は安息日ではない
新約に入ると状況は変わりました。主イエスは安息日に会堂に入られ、聖書を読まれました(ルカ4:16)。彼は会堂に入って、人に教えられました(マルコ1:21)。使徒たちもまた安息日に会堂に入って、聖書について説きました(使徒17:1-3)。このことから、安息日には消極的な休みがあるだけでなく、積極的な働きがあることを見ることができます。もともとそれは体を休める日でしたが、新約になるとそれは霊的な事柄を追求する日と変わりました。これは一つの前進です。
もしわたしたちがよくよく聖書を読むなら、聖書における神の啓示は進歩していることを見いだすことができます。以前の聖書を読むための四つの基本原則と実践的ガイド – 聖書の読み方 – 初信者シリーズ 7 の記事で、聖書を読む時には「事実を探し出す必要がある」ことを語りました。それは、事実の中に光があるからです。事実に変更があったのですから、新しい光があるのです。安息日についてもそうです。
聖書は創世記において「神はその第七日目を祝福し」(創世記2:3)と言っています。しかし、主イエスが復活された時、聖書は「週の初めの日」(マタイ28:1)と言っています。聖書は主イエスの復活の日を「第七日目」とは言わずに「週の初めの日」と言っています。これは神が「週の初めの日」を「安息日」に代えられたと言っているのではありません。しかし、神がわたしたちの注意を転じて、「週の初めの日」に心を向けるようにと願っていることを聖書ははっきりと見せています。
安息日は福音の予表です。福音の実際であるキリストが来たので、その予表は過ぎ去りました。安息日の原則は福音です。それはささげ物の原則が十字架であるのと同様です。旧約でささげ物に用いられた牛や羊は、みな神の小羊である主イエスを予表しています。主イエスが来られたので、牛や羊は用いられなくなりました。もし今日も牛や羊を引いてきてささげ物にするなら、それは十字架を認識していないということです。同様に、福音はすでに来たのですから、人は福音によって神の御前で安息することができるのです。神は、ご自身の御子の十字架上での贖いを通して、わたしたちのためにすべてのみわざを成し遂げてくださったのですから、神はわたしたちという人が先に何かをするように命令されるのではなく、まず安息するようにと命じられたのです。今日、牛や羊のささげ物がないように、安息日もありません。安息日は旧約における予表です。新約では、この予表はすでに成就したのです。
Ⅱ. 主日の根拠
旧約では、神は七日間の一日、すなわち第七日を選び、それを聖なる安息日と定められました。新約になると、旧約の第七日はすでに過ぎ去りましたが、七日間の中から一日を選ぶ原則はやはり継続しています。しかしながら、新約には別の日があります。安息日が主日になったのではありません。旧約の時、神は一週の中から第七日を選ばれました。新約では、神は一週の中から第一日を選ばれたのです。神は第七日を第一日と呼んだのではなく、別の日を第一日とされました。
詩篇第118篇22節から24節はとても重要です。「家を建てる者たちの捨てた石、それが隅のかしら石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。これは、主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼう」(原文)。ここに「家を建てる者たちの捨てた石」という言葉を見ます。石が役に立つかどうかは、家を建てる者たちの決めることです。家を建てる者たちがこの石は使えないと言えば、それは使えないのです。しかし、不思議なことがあります。神は彼を、すなわち「家を建てる者たちの捨てた石」を、「隅のかしら石」とし、土台とされました。神は最も重要な責任を彼の上に置かれたのです。24節はさらに不思議な言葉です。「これは、主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼう」。これは家を建てる者たちの捨てた石が隅のかしら石となった日こそ、主が設けられた日であると言っています。
それでは、どの日が主の設けられた日なのでしょうか?使徒行伝第4章10節から11節は言います、「あなたがた一同も、イスラエルのすべての民も知っていただきたい。あなたがたが十字架につけ、神が死人の中から復活させたナザレ人イエス・キリストの御名の中で、この名の中で、この人が、あなたがたの前に健やかになって立っているのです。この方は、あなたがた、家を建てる者たちに捨てられ、隅のかしらになった石です」。10節は、「あなたがたが十字架につけ、神が死人の中から復活させた」と言い、11節は、「あなたがた、家を建てる者たちに捨てられ、隅のかしらになった石です」と言います。家を建てる者たちが捨てた時とは、主イエスが十字架につけられた時です。神が彼を隅のかしら石とされた時とは、神が彼を死人から復活させた時です。言い換えれば、この石は、主イエスの復活の時に、隅のかしら石となったのです。ですから、「主の設けられた日」とは、主イエスの復活の日です。
ここでわたしたちが見るのは、わたしたちの主日は、旧約の律法の下にある安息日とは全く異なっています。旧約の安息日は、これをしてはならない、あれはすべきではないと、みな消極的です。しかし、神は新約時代に設けられた主イエスの復活の日は、楽しみ喜ぶようにと言っておられます。ですから、主日の特徴は、積極的な命令があるだけであって、消極的な命令はないのです。
七日間の中から神は特に一日を選び出し、この日を特別な名前で呼んでいます。啓示録第1章11節はそれを「主日」と呼んでいます。「主日」は聖書で述べられている「主の日」であるという人がいますが、それは間違っています。原文では「主日」と「主の日」とは全く異なります。「主日」は週の第一日であり、「主の日」は主の再来の日です(第一テサロニケ5:2、第二テサロニケ2:2、第二ペテロ3:10)。もう一面において、古代の教父たちの著作から、「主日」が週の第一日を指し、教会の集会の日とされていることを証明する多くの材料を見つけることができます。古代教父たちの著作の中の多くの資料が、初代教会の時代から第四世紀までずっと週の第一日に集会していたことを証明しています。古代の教会の主日に関する資料
Ⅲ. 主日は何をすべきか
主が設けられた日である主イエスの復活の日、すなわち、週の第一日(主日)にわたしたちは何をすべきなのでしょうか?主日に何をすべきかについて聖書は、三つのことを重要視しています。第一は、喜び楽しむこと。第二は、主を記念すること。第三は、主にささげものをすることです。一つ一つを詳しく見ていきましょう。
1. 楽しみ喜ぶ
詩篇118篇24節は言います、「これは、エホバが設けられた日である。わたしたちは喜び躍り、それを喜び楽しもう」。ここに啓示されているように、すべての神の子たちが週の第一日に取るべき態度は、喜び楽しむことです。わたしたちの主は死から復活されました。これは主が設けられた日(主日)であり、わたしたちはこの日が来るたびに喜び楽しむという態度を持ち続ける必要があります。この日はわたしたちの主の復活の日であり、このような日は他にありません。ですから、主日に喜び楽しむことは自然な反応であるべきです。
2. 主を記念する
第二に、使徒行伝第20章7節は言います、「そして週の初めの日、わたしたちがパンをさくために集まった時・・・」。原文の文法によれば、ここの「週の初めの日」は、ある週の初めの日を限定して指しているのではなく、彼らが毎週の初めの日にパンをさくために集まったことを意味します。当時すべての教会は、週の初めの日になると自然にパンをさくために集まって、主を記念していました。週の初めの日は、わたしたちが主にまみえる日です。週の初めの日に必ずしなければならないことは主を記念することです。わたしたちが週の初めの日にまず主の御前に行くのです。主日は週の第一日です。月曜日は実は週の第二日です。
パンさきには、聖書では二つの意義があります。一つは主を記念することであり、もう一つはわたしたちと神のすべての子供たちとの間に交わりがあることを表明することです。パンさきについてはさらに詳しく書いた記事があるので、こちらをご覧ください。
3. 主にささげものをする
コリント人への第一の手紙第16章1節と2節は言います、「聖徒たちへの贈り物を集めることについては、わたしがガラテヤの諸召会に指示しておいたように、あなたがたも行いなさい。週の初めの日に、各自は得た繁栄に応じて手元に蓄えておき、わたしが行った時に集めることのないようにしなさい」。ここで、週の初めの日になすべき第三の事をみます。パウロはここでガラテヤに在る各教会に指示しておいたように、コリントに在る教会にも指示しています。これは使徒たちの時代には、週の初めの日が特別な日であったことを明らかに示しています。週の初めの日にはパンをさいて主を記念することがあり、また聖徒たちのために献金することがあります。週の初めの日ごとに、各自はその経済的に恵まれたところに応じて主にささげるべきです。一方でパンさきがあり、一方で献金があります。一方でわたしたちは主がどのようにご自身をわたしたちに与えてくださったかを記念し、もう一方でわたしたちもまた、この日に主にささげるのです。
わたしたちは、何も考えないで少しのお金を取り出して献金箱に投げ入れるべきではありません。真心をもって家でよく計算し、家で準備し、あるいは家で包んで、敬虔な方法で献金箱に入れるべきです。パウロはここで、献金は計画的になすもの、定期的になすものであることを見せています。週の初めの日ごとに、自分の経済的に恵まれたところに応じて取り出し、主に言う必要があります、「主よ、あなたはこんなにも豊かに与えてくださいました。主よ、わたしは得たものからあなたにささげます」。恵みが多ければ多く献金し、少なければ少なく献金します。パンさきは厳粛な事であり、献金もまた厳粛な事であることを、知らなければなりません。
まとめ
主は特別に一週の中から一日を取り出して、それを主日と呼んでいます。それは週の初めの第一日です。ですから、わたしたちの日曜日に位置する日は主日です。わたしたちの主日と安息日は異なります。安息日はしてはいけない事に重きがあります。しかし、わたしたちの主日は、体の安息のためではなく、働きのためでもありません。他の日にやってよい事は、主日にも行うことができます。他の日にやってはいけない事は、主日にもやってはいけません。
聖書は、主日に喜び楽しむようにと、もっぱら主の御前に来て恵みを受け、主を記念し、主に仕え、ささげるようにと告げています。わたしたちは一生の間、この主日を取り出して特別な日としなければなりません。少なくとも週の初めの日はすべて取り出して、主のためとしなければなりません。この日はわたしたちの日ではありません。この日は「主日」です。この時間は、わたしたちの時間ではありません。この時間は、主の時間です。この日は主にささげた日であり、それを主日と呼ぶのです。
ヨハネは啓示録でこのように言いました。
わたしは主日に霊の中にいた。
啓示録 1章10節
どうか多くの人が、「わたしは主日に霊の中にいた」と言う事ができますように。
参考資料
ウォッチマン・ニー全集 第三期 第四十八巻 初信者を成就するメッセージ(一)第十四編
出版元:日本福音書房
※ 本記事で引用している聖句に関して、明記していなければすべて回復訳2015からの引用です。
「オンライン聖書 回復訳」
添付資料
古代の教会の主日に関する資料

2025-03-23 | 初信者成就シリーズ
(この記事は7,830文字で、16分で読み終えることができます。)
クリスチャンには地上で一つの基本的な権利があります。それは祈りが答えられるということです。あなたが主イエスを信じ、再生されたなら、神は一つの基本的な権利を与えられます。それは、あなたが神に求めることができ、神はあなたの祈りを聞かれるということです。ヨハネによる福音書第16章には、わたしたちが主の御名の中で求める時、神は答えてくださり、わたしたちの喜びが満たされる、と言っています。ですから、わたしたちが絶えず祈るなら、地上で喜んでいるクリスチャンになることができます。
もしあなたがいつも祈っているのに、「神は祈りを聞いてくださらない」と感じているのであれば、それはあなたに問題があることを知らなければなりません。また。あなたがクリスチャンになって何年も経つのに、一、二度しか祈りが聞かれたことがないというなら、それはあなたという人に欠陥があることを証明しています。この記事では、神が祈りに答えられる条件と祈りを実行する方法を共に学んでいきたいと思います。
Ⅰ. 祈りが答えられる条件
祈りが答えられる基本的な条件は多くありません。もし、このいくつかの条件にしたがって祈るなら、祈りは答えられると信じます。これから話すことはすべて基本的な条件ですから、わたしたちはそれらに注意を払うべきです。この基本的な条件は五つあります。
- 求める
- 悪い求め方をしてはいけない
- 罪を対処する
- 信じる
- ずっと求め続ける
これら一つ一つを詳しく見ていきましょう。
A. 求める
すべての祈りはみな、神の御前で真実に求めるものでなければなりません。主は言われます、「求めよ、そうすれば、あなたがたに与えられる。捜せ、そうすれば、見いだす。門をたたけ、そうすれば、あなたがたに開かれる」(マタイ7:7)。例えば、ここに一つのものがあり、あそこに一つのものがあるとします。それでは、あなたはいったい何が欲しいのですか?神は、あなたが何を欲しがっているのか、何を求めているのかを知ってはじめて、あなたにそれを与えられます。ですから、求めるという意味は、ある特定のものを求めることです。
たとえば、今日あなたが何かが欲しければ、父親に向かってその何かを言うでしょう。レストランに行けば、何を食べたいかを店員さんに言うでしょう。しかし、奇妙なことに、人は神の御前に行って何が欲しいかを言わないのです。ヤコブは手紙の中でこのようにいいました、「あなたがたが得ることがないのは、求めないからです」(ヤコブ4:2)。多くの人に祈るという行為はありますが、求めるものがありません。祈る時、必ず何が欠けているか、何が欲しいかを言い出さなければなりません。これが第一の条件です。
B. 悪い求め方をしてはいけない
わたしたちは神の御前で求めるべきですが、二番目の条件があります。それは悪い求め方をしないことです。「求めても得られないのは、・・・悪い求め方をするからです」(ヤコブ4:3)。わたしたちは、必要があるから神に求めるのであって、何の必要もなしに、度を超えて気ままに求めることはできません。自分の欲望や肉にしたがって、不必要な事物を勝手に求めてはいけません。
悪い求め方をするとは、あなたの度量を超えて、あなたの必要を超えて、あなたの真の欠乏を超えて求めることです。あなたが必要があれば、神に求めることができます。あなたの必要を超えて求めることは、悪い求め方をすることです。わたしたちは自分の正当な範囲内で祈ることを学ぶべきです。これが第二の条件です。
C. 罪を対処する
ある人は、求めることは求め、また悪い求め方もしないのですが、それでも神は彼の祈りを聞かれません。それは基本的な妨げ、すなわち神と彼との間に罪があるという妨げがあるからです。詩篇にはこのような御言葉があります。「もしも私の心にいだく不義があるなら、主は聞き入れてくださらない」(詩篇66:18)。人がもし心に不義をいだいているなら、主は聞いてくださいません。「心に不義がある」とは、捨てることのできていない罪があるということです。自分では知っているのに、心の中に保留している罪があるということです。一つの罪があるだけで、あなたの祈りが神に聞かれないほどの妨げとなります。
箴言第28章13節はいいます、「自分のそむきの罪を隠す者は成功しない。それを告白して、それを捨てる者はあわれみをうける」。あなたは主に言わなければなりません、「心にいだいていた不義を、わたしは手放せないでいました。今わたしを赦してください。わたしはそれを捨てたいのです。この罪から離れるようにわたしを救ってください。」あなたが神の御前で罪を告白するなら、主はあなたを赦してくださいます(第一ヨハネ1:9)。そうすれば、あなたの祈りは神に聞かれます。
D. 信じる
もう一つの条件があります。それは積極面で「信じる」ことです。主イエスはこのように言われました、「あなたがたが祈って求めるものはすべて、受けたと信じなさい。そうすれば、そのとおりになる」(マルコ11:24)。祈り求めるだけで終わりではありません。祈り求め、そして信じるのです。もう受けたと信じるなら、そのとおりになります。主はここで、「受けたと信じるなら、そのとおりになる」と言われました。主は「必ずそのようになると信じなさい」とは言っていません。「もう受けた」と信じるのです。信じるとは「もう受けた」と信じることです。
多くのクリスチャンは「信じること」に関して間違っています。この「信じる」を「もう受けた」から取り外して、「そのとおりになる」の下にくっつけるのです。彼らは、「そのとおりになると信じる」ことを信仰であると勘違いしています。違います。「もう受けた」と信じるのです。祈りに関する信仰とは何でしょう?それは、神があなたの祈りをすでに聞かれたという確信です。あなたがひざまずいて祈っている時、ある時点になって「神に感謝します!神はわたしの祈りを聞いてくださいました。神に感謝します!このことはもう解決しました」と言ってしまいます。これが信仰であり、「もう受けた」です。
例えば、あなたが一人の病人のために祈るとします。彼は「神に感謝します!わたしはいやされました」を言います。熱はまだ高く、少しの変化もないのですが、彼の内側ではっきりしていさえすれば、もう何の問題もないのです。もし彼が「ああ、わたしは主がこの病気をいやしてくださると信じます」と言うなら、その次になおも多くの「信じる」がなければならなくなります。主イエスは言われました、「もう受けたと信じなさい。そうすれば、そのとおりになる」。主は「そのとおりになると信じれば、そのとおりになる」と言われたのではありません。言葉を逆にしてはいけません。
信仰についてマルコによる福音書から具体的な例を用いてさらに詳しく見てみましょう。マルコによる福音書には、祈りに関して特に役に立つ三つの言葉があります。第一は主の力の問題であり、第二は主の意志の問題であり、第三は主の行為の問題です。
1. 主の力 – 神はできる
マルコによる福音書第9章で、自分の息子が口の利けない霊にとりつかれ、それをイエスの元に連れてきた父親が言いました、「もしあなたに何かできるのでしたら、わたしたちをあわれんでお助けください」(マルコ9:22)。主イエスは言われました、「『もしあなたにできるなら』と言うのか。信じる者にはすべての事ができるのだ」。これはできるかできないかの問題ではなく、主の力を信じるか信じないかの問題です。
信じることについて、第一に解決しなければならない問題は、人は困難の中にある時、疑いに満ち、神の力を信じることができないということです。「人にはできない事でも、神にはできる」(ルカ18:27)のです。
2. 主の意志 – 神はそうされる
確かに彼はおできになります。しかし、どのようにしてわたしたちは、主がわたしをいやしてくださるかを知ることができるのでしょうか?わたしたちは主の意志を知りません。主はわたしたちをいやしてくださるかもしれないし、いやしてくださならいかもしれません。どうしたらいいのでしょうか?もう一つの物語を見てみましょう。
マルコによる福音書第1章40、41節はいいます、「 すると、一人のらい病の人がイエスの所に来て、彼に懇願し、ひざまずいて言った、『あなたがそのつもりであるなら、(みこころであれば、他訳)わたしを清めることができます』。イエスは深くあわれんで、手を伸ばして彼に触れ、そして言われた、『わたしは良しとする。清くなりなさい!』」。ここに神がしてくださるかどうかの問題があります。もし神にわたしたちの病をいやす気持ちがなければ、神の力がどんなに大きくても、それはわたしたちと何の関係もありません。しかし、ここではイエスは深くあわれんで、触れて癒してくださったことを見ます。ですから、解決を要する第一の問題は神ができるということを信じることであり、解決を要する第二の問題は、神はしてくださるということを信じることです。らい病人は主に求め、主は彼を清くされました。わたしたちの主が病をいやされないことはあるでしょうか?
3. 主の行為 – 神はすでに成された
「神はできる」「神はしてくださる」と知っただけではまだ不十分です。もう一つは「神はすでに成された」と信じることです。これは先ほど取り上げた事柄です。信仰とは、「神はできる」「神はそうされる」「神はすでに成し遂げられた」と信じることです。信仰は待ち望むのではありません。待ち望むとは、将来のそうなることを期待することであり、信じるとは、それがすでに成されたと考えることです。「神はすでに成された」を信じるなら、自然と神への感謝が出てくるでしょう。
E. ずっと求め続ける
祈りには、注意しなければならないことがあります。それは、継続しなければならず、やめてはいけないということです。「彼らが絶えず祈るべきであり、また失望しないように」(ルカ18:1)。ある祈りは、ずっと祈り続ける必要があります。主が煩わしいと感じ、わたしたちの祈りを聞かないではいられなくなる程度にまで祈り込むのです。
これはわたしたちへのテストです。というのは多くの場合、わたしたちの祈りは一週間も続かないからです。それは、真にわたしたちが求めていなかったことを暴露します。ある種の切迫した環境にあり、ある必要な状況の下にあって、心がそれによって動かされてこそ、ずっと祈り続けることができます。
早見表
祈りが答えられる条件
| 条件 | 説明 |
|---|
| A.求めること | 祈りにおいて、神に対して具体的に願いを伝えること。 |
| B.悪い求め方をしないこと | 自己中心的な欲望に基づかず、正しい態度で求めること。 |
| C.罪を対処すること | 神との妨げとなる罪を認識し、告白して捨てること。 |
| D.信じること | 祈りが神に聞かれ、答えがすでに与えられたと信じること。 |
| E.求め続けること | 一度で答えが得られなくても、祈りを続ける忍耐を持つこと。 |
Ⅱ. 二段階の祈り
祈りには二つの段階があることを知らなければなりません。第一段階は、約束がないところから祈って約束を得るまで、神の言葉がないところから祈って神の言葉を得るまでです。すべての祈りの開始の時は、みな神に求めるものであって、ずっと求め、三年、五年と費やしてずっと求めなければなりません。この第一段階は「求める期間」です。
第二段階は、約束があって、その約束が実現するまで、神の言葉を受けてから、その言葉が成就するまでです。この第二段階は「賛美の期間」です。この段階では、祈り求めるのではなく、賛美すべきです。第一段階では祈り求め、第二段階では賛美します。第一段階は、言葉がないところから祈って言葉があるまでであり、第二段階は、言葉があったらすぐに主を賛美し、求めていた物が手に入るまで賛美し続けます。これが祈りの秘訣です。
多くの人が理解している祈りには二つの事実しかありません。一点は、わたしは持っていない、わたしは祈るという「求めた」という事実です。もう一点は、わたしは得た、神がわたしに与えたという「受けた」という事実です。例えば、わたしが主の御前で腕時計を与えてくださるように求めるとします。数日たって、主はわたしに一つの腕時計を下さいました。これは腕時計を持っていない状態から求めたという事実があり、腕時計が与えられたという状態という受けたという二点があるだけです。しかし、真の祈りにはその間にもう一点、「信じた」という事実があるべきです。多くのクリスチャンがこのことを知りません。
わたしは祈って腕時計を求めます。ある日わたしは、「神に感謝します。神はすでにわたしの祈りを聞かれました」といいます。この時、依然としてわたしの手元には何もありませんが、内側では、得たことがはっきりしました。そして、数日後に腕時計が手に入るのです。わたしたちは「求めた」「受けた」という二点を見るだけでなく、「信じた」という三点目を見なければなりません。何も持っていない状態から「求める」ということから、それを受けるまでの間にもう一点、神が言葉を与えられた、約束してくださった、わたしは信じた、わたしは喜んだ、があるのです。まだ手元には何もないかもしれません。しかし、霊の中ではすでに得ているのです。クリスチャンにはこの霊の中で得るということがあるべきです。霊の中で得たこの種の感覚がなければ、それは信仰がないことです。
ある時、わたしは主から家族の救いのために祈るように導かれました。わたしは両親と姉と弟のために祈り始めました。わたしは数日間、主の御前に出て、一人一人の名前を挙げて祈りました。これは求める期間でした。それから数週間後、わたしは主のあわれみによって神がわたしたちに与えられた救いの約束は、個人を単位としているのではなく、家を単位としていることを見ました。使徒行伝16章31節はいいます、「すると彼らは言った、「主イエスを信じなさい.そうすれば、あなたもあなたの家族も救われます」。聖書の中に、神は人を家族ごとに救われるという一つの基本的な原則があります。例えば、ノアの家族(創7:1)、過越にあずかる家族(出12:3-4)、遊女ラハブの家族(ヨシュア2:18-19)、ザアカイの家族(ルカ19:9)、コルネリオの家族(11:14)、ルデヤの家族(15節)、ここの獄吏の家族、第18章8節のクリスポの家族のようにです。わたしはこの主の言葉を受けてから、求める祈りから賛美する祈りに変わりました。わたしはまだ何も得ていませんが、霊の中にはすでに与えられたという信仰があるのです。
なぜ二つの段階に分けるのでしょうか?それは、物がないところから祈って信仰を得たのに、もしまた祈り求めるなら、信仰はかえって逃げ去るからです。ですから、信仰を得たならすぐに賛美をしなければなりません。信仰があって物がまだない時、賛美をもって神に催促すべきであり、祈り求めることによって神に催促するべきではありません。
早見表
| 段階 | 説明 |
|---|
| 第一段階:求めること | 神に対して具体的に願いを求める段階。 |
| 第二段階:賛美をささげること | 霊の中で約束が与えられ、まだ手元には何もないけれども賛美をささげる段階。 |
| 第三段階:実際に受けること | 実際に願ったものが与えられる段階。 |
Ⅲ. 祈りを実行する方法
最後にどのように祈りを実行するかの具体的方法を交わりたいと思います。まず重要なことは、祈る前に一冊の祈りのノートを用意することです。一年に一冊のノートを用意し、祈りを記載します。そして、各ページを四つの項目に区切ります。第一項目は祈りを始めた日付、第二項目は祈る事柄、第三項目は答えられた日付、第四項目は神がどのように祈りを聞かれたかです。こうすれば、一年の間にどれだけあなたが神に要求し、どれだけ神が聞かれたか、またどれだけ残っているかがわかります。
祈りのノートを活用することによって、祈りが神に聞かれているかどうかを知ることができます。神の答えが止まったら、必ずあなたに欠陥があります。ノートに記された祈りはすべて、神の答えを得るまで祈り続けなければなりません。神があなたのその祈りは神のみこころではないと示された時だけ、停止するのです。それ以外は、得るまで祈り続け、決してたるんではいけません。
祈りのノートを用いる時に注意すべきことがあります。ある事柄は毎日祈る必要がありますが、ある事柄は一週間に一回祈ればいいことです。これは、あなたの祈る項目がどれだけあるかで決まります。あなたの求めるものが少ない場合、ノートに書かれた項目を毎日祈ることができます。項目が多ければ少し工夫して、月曜日には何項目祈り、火曜日に何項目祈ることにします。祈りのノートを活用するためには専一の祈りがなければなりません。あなたは自分自身を訓練して、専ら(もっぱら)祈るための時間を持つべきです。
祈りには、祈る側と祈られる側の両側があります。祈られる側に変化して欲しいなら、祈る側の人がまず変化しなければなりません。もし祈り続けているのに一向に状態の変化が見られないなら、神の御前で尋ね求めて言わなければなりません、「主よ!わたしにはどんな変化が必要なのでしょうか?わたしにまだ対処していない罪があるのでしょうか?手放さなければならない好き好みがあるのでしょうか?わたしには学ばなければならない学課があるのでしょうか?」自分自身が変化していないのに、他の人の変化を期待することはできません。
まとめ
あなたが主を信じ、受け入れるなら基本的な権利を与えられます。それは、あなたが神に求めることができ、神はあなたの祈りを聞かれるということです。しかし、この祈りが答えられるためには条件があります。第一に求めること。第二に悪い求め方はしてはいけないこと。第三に罪を対処すること。第四に信じること。第五に求め続けることです。
あなたの祈りには三つの段階があるべきです。第一段階は、求めることです。第二段階は、約束が与えられ、まだ手元には何もないけれども賛美をささげることです。そして第三段階で、実際に受けることです。何もない時には求める時期です。求め続けるなら霊の中で信仰(確信、約束)が与えられます。この時から賛美の時期に移行します。そして、実際に手に入れるまで賛美し続けます。
具体的に祈るために祈りのノートを用意すべきです。専一な祈りのために一日に30分間の祈りの時間を確保することをおすすめしたいと思います。前回の聖書を読む実行を30分、この祈りの実行を30分、一日に合計1時間の時間を主にささげるなら多くの収穫を得るでしょう。聖書を読むための四つの基本原則と実践的ガイド – 聖書の読み方 – 初信者シリーズ 7
参考資料
ウォッチマン・ニー全集 第三期 第四十八巻 初信者を成就するメッセージ(一)第十編
出版元:日本福音書房
※ 本記事で引用している聖句に関して、明記していなければすべて回復訳第3版(2015)からの引用です。
「オンライン聖書 回復訳」

2025-03-20 | ウォッチマン・ニー
ウォッチマン・ニー(倪柝聲:ニー・トゥォーシェン)は、中国において神に大きく用いられた主のしもべであり、多くの霊的著作を通して世界中のクリスチャンに深い影響を与えました。彼の生涯は神の召しに忠実に応答し続け、真理の啓示と実践において大胆かつ誠実でありました。彼の働きと召会(教会)の回復のための務めは、今なお多くの人々の信仰の土台となっています。
以下はウォッチマン・ニーの生涯年表です。
Ⅰ. ウォッチマン・ニー(倪柝聲)の生涯年表
第一期:初期の召命と真理の発見(1903-1927年)
- 1903年: 中国福建省福州にて敬虔なクリスチャン家庭に生まれる。
- 1920年4月:17歳で救われ、主に仕えるよう召される。
- 1921年:バプテスマの真理を知り、マーガレット・バーバーと母と共にバプテスマを受ける。
- 1922年:パンさき(主の食卓)に関する真理を知り、福州でパンさき集会を始める。また、宗派から離れ、地方召会を設立。
- 1923年:『現在の証し』雑誌を創刊。
- 1924年:杭州を訪問し、各地で福音を宣べ伝える。
- 1925年10月:母とマレーシアのシティアワンを訪問。『クリスチャン』雑誌を出版開始。東南アジア最初の召会を設立。
- 1926年:廈門、同安、南京などで召会を設立、南京の大学で働く。『霊の人』執筆開始。
- 1927年:上海の召会を設立、上海福音書房を成立。
第二期:国際的な務めの拡大と真理の出版(1928-1939年)
- 1928年:上海で第一回勝利の特別集会を導く(主題:「神の永遠のご計画とキリストの勝利」)。
- 1929年:『霊の人』完成・出版。『聖書についてのメッセージ記録』『小さな群れの詩歌』発行。
- 1931年10月:上海で第二回勝利の特別集会(主題:「新契約と神の知恵」)。
- 1932年6月:煙台(チーフー)で召会設立。
- 1933年:ヨーロッパ(フランス、英国)、カナダ、米国を訪問し、各地で語る。年末に『ニューズレターの収集』を発行。
- 1934年:第三回特別集会(主題:「キリストは神の中心性と普遍性である」「神の勝利者」)と第四回特別集会(杭州、主題:「どのようにして勝利者となるか」「霊的戦い」)。
- 1936年:上海郊外の真姑に訓練センター建設。
- 1937年:上海で『正常なキリスト者の召会生活』のメッセージを解き放つ。マニラ、シンガポール、マレーシア訪問。『開かれた門』出版。
- 1938年:英国訪問、T・オースチン・スパークスと会う。
- 1939年:上海の友華村で訓練を実施。
第三期:訓練と迫害の中での忠実さ(1948-1972年)
- 1948年:上海の召会を復興させる。鼓嶺で第一回訓練指導。
- 1949年:鼓嶺で第二回訓練指導。
- 1950年:香港、廈門、チーフーの召会を訪問。
- 1952年:共産主義政権により主のために投獄。
- 1972年:獄中にて主に召される。享年70歳。
ウォッチマン・ニーの働きは、中国国内外の教会に大きな影響を与え、今もその霊的遺産が世界中のクリスチャンに継承されています。
参考書籍
今の時代における神聖な啓示の先見者 ウォッチマン・ニー
出版元:日本福音書房
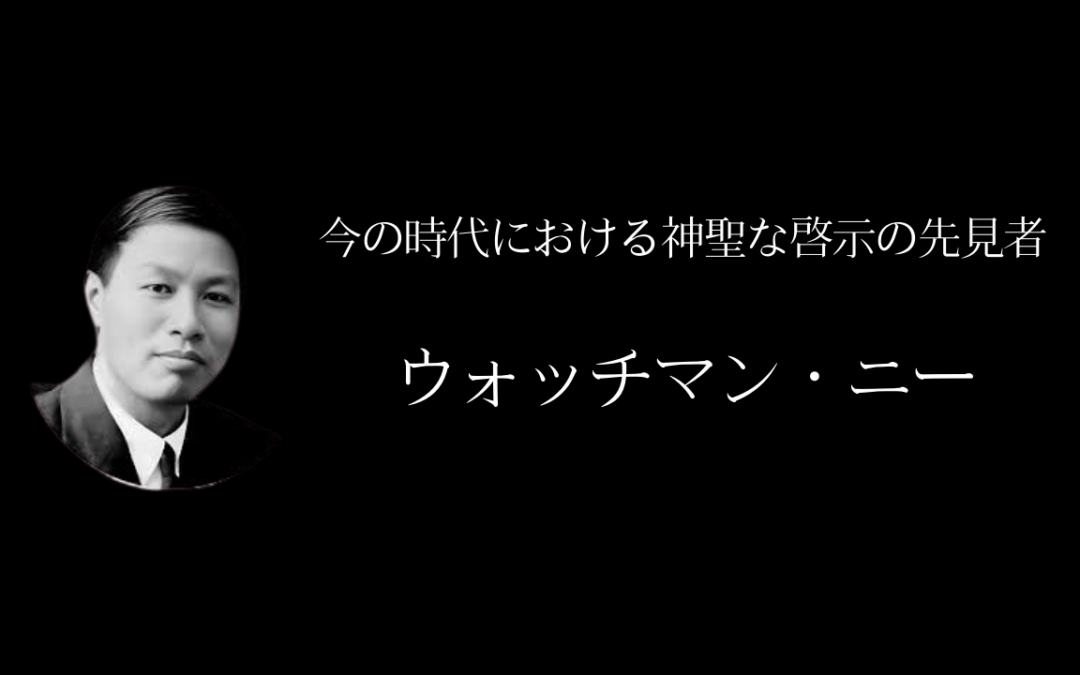
2025-03-19 | ウォッチマン・ニー
ウォッチマン・ニー(倪柝聲:ニー・トゥォーシェン)彼は、20世紀の中国において神に大きく用いられた主のしもべです。彼は中国大陸において1920年の17歳でクリスチャンになり、執筆を始めました。彼は約30年間の務めを通して、この時代における主の動きのために、主から彼のからだへ与えられたユニークな賜物であることが明らかされました。1952年に彼は共産主義政権によって投獄され、1972年の死まで監獄に入れられたままでした。彼の言葉は、世界中のクリスチャンたちへの霊的な啓示と豊富な供給の源となっています。
Ⅰ. ウオッチマン・ニー (1903-1972)
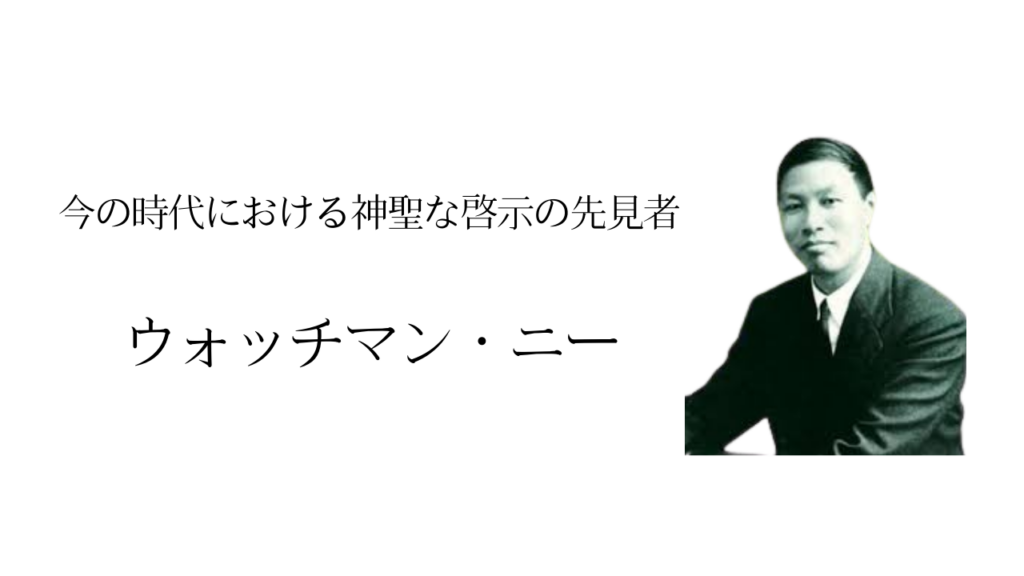
ウォッチマン・ニーは1903年、中国・福州で敬虔なクリスチャンの家庭に生まれました。彼の祖父、倪玉成(ニー・ユーチェン)は福州のアメリカ会衆派の大学で学び、福州北部の会衆派の中国人の初代牧師になりました。祖母や両親も熱心なクリスチャンとして教育を受け、キリスト教に深く根ざした家庭環境の中で育ちました。彼自身も福州の聖公会三一学院という、英語と中国語の教育水準が非常に高い教育機関で学び、両言語に熟達しました。
1920年代になると、中国全土で福音宣教が活発になり、多くの学生たちが福音を受け入れ、霊的な覚醒が広まりました。そのような霊的高揚の中で彼もまた17歳の時に劇的な回心を経験し、自らの人生をキリストに完全に委ねました。回心後、彼は新たに英語名をウォッチマン・ニー(Watchman Nee)、中国語名を倪柝聲(ニー・トゥォーシェン)に改名しました。「ウォッチマン」とは「見張り人」を意味し、夜の暗闇の中で時を告げ、人々を真理へと目覚めさせる役割を表しています。
A. ウォッチマン・ニーの務め
彼の働きは、当時の中国における形式的で伝統的なキリスト教のあり方に疑問を投げかけ、単に宗教的知識を持つことではなく、「キリストを命として内側で実際的に経験すること」を中心テーマとしました。彼はまた、教派や宗派を超えてキリストのからだである召会(教会)の真理を追求し、『正常なキリスト者の生活』『霊の人』『キリスト者の標準』をはじめ、多くの深遠な著作を通じて、真の霊的な生活の道を示しました。
しかし1952年、中国共産党による宗教弾圧のために逮捕され、約20年間にわたり投獄されました。獄中で多くの苦難を経験しながらも、彼は信仰を守り通し、1972年に殉教しました。ウォッチマン・ニーの肉体は滅ぼされましたが、彼が残した霊的遺産や著作は、中国国内のみならず世界中のクリスチャンに影響を与え続けています。
彼の人生と働きは、主の地上における回復の働きを進めるための特別な賜物であり、中国だけでなく、全世界の教会に霊的な覚醒をもたらす礎となりました。今日でもウォッチマン・ニーの著作や思想は、多くのクリスチャンが真の霊的経験を深めるための貴重な導きとなっています。
さらに詳しく知りたい方は、『キリスト者の標準』『神の福音』『勝利を得る命』『霊の解放』『歌の中の歌』などの著作を手に取ることで、ウォッチマン・ニーの教えや霊的洞察に触れることができます。また、ウォッチマン・ニーの伝記『今の時代における神聖な啓示の先見者 ウォッチマン・ニー』なども、彼の人生と働きをさらに深く理解するための良書です。
Ⅱ. ウォッチマン・ニーの書籍
A. 神の福音
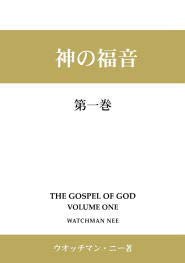
B. 勝利を得る命
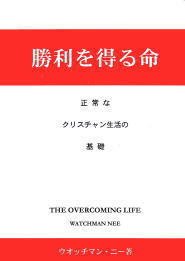
C. 霊の解放
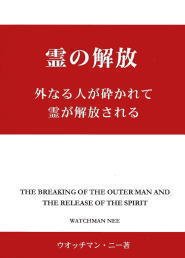
D. 歌の中の歌
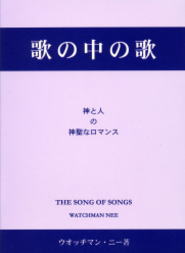
E. キリストの奥義
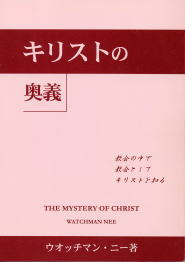
F. 神聖な啓示の先見者

これらの書物は日本福音書房にてお買い求めいただけます。
出版元:日本福音書房
参考書籍
今の時代における神聖な啓示の先見者 ウォッチマン・ニー
出版元:日本福音書房